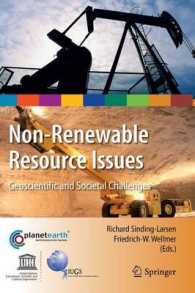内容説明
ウィトゲンシュタイン、死の直前の考察。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
36
色彩がなぜ問題になるのか。色とは、一見その物体に帰属しているようにみえ、実のところ我々の側にあるものだからでしょう。排中律のような厳密さえも越境してしまい、主体からはそうとしかいいようのない様相でその物体が見える。そうであれば、見る主体によって色は異なるといいたいが、他者が自分と同じような色としてみえているかは、原理的には分かりようが無い。独我論的、言語ゲーム的論点を持ち合わせていて、考えれば考えるほど真理が繰り延べられていく感覚に晩年のウィトゲンシュタインは関心を持ったのではないでしょうか。2020/04/11
CCC
11
色がどのように認識されているのかを、科学的視点を切り離して言語ゲームの観点から考察している。色盲者とそうでない者が同じ記述をした場合になにが違っているのか。特定の色を示す際にこの表現は適切でこの表現はナンセンス、などと言えるのなぜか。あるいはナンセンスとされる表現も自分と感覚が違う者にとってはナンセンスと言えるのか、など多くの論点、疑問がならんでいる。答えを出してくれるような本ではない。クオリア論の前段階みたいな感じも受けたが、そういう便利ワードがないからこその深い考察になっていたと思う。2022/04/26
ymazda1
3
小さい頃、なぜか左目と右目から見える色が違ってて、そのせいか、「人によって色の見え方が違うなら、暖かい色とかってなんなんだ?」みたいな疑問が自分の中にあったりしてて、この本をたまたま書店見つけたときは「おんなじことをマジメに考えてた人がいた!」と思わず感動して衝動買いして読んでしまった。
roughfractus02
2
私の知覚する白とあなたの知覚する白は同じか? 本書は、著者の追求した「内的関係」(それ自体に必然性はないが、他のものに置き換えなければならない必然性もない)によって形成される規則について、ゲーテ『色彩論』が見出した色相環の規則と対照しながら思索した350の断章から成る。言語と世界が質が異なるにもかかわらず密接に関連する点について、システム論がカップリングという概念を提示し、二重否定によって導出される彼の「内的関係」の規定の仕方の粗雑さを批判する。が、その粗雑さこそ日々起こる「内的関係」の質のように思える。2017/02/20
真
0
タイトル通り色彩について延々考える。難しかったが興味深かった。2016/12/23