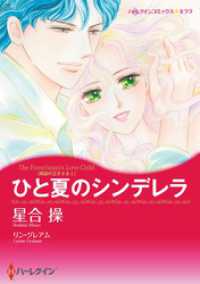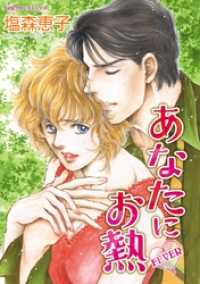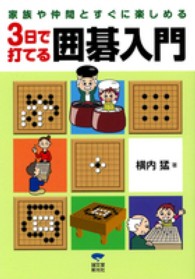内容説明
産業革命のあと、フランスで腕木通信と呼ばれる技術が誕生したのが1794年。そして、レイ・カーツワイルが主張する「シンギュラリティ」、すなわちコンピュータの能力が人間を超え、これまでとまったく異なる世界が現れるのが2045年とされている。本書は、この間250年の物語だ。情報技術の過去を振り返り、現在を検証し、将来を構想する。
目次
プロローグ 生態史観から見る情報技術
第1章 腕木通信が空を駆ける―近代的情報技術の幕開け
第2章 電気を使ったコミュニケーション
第3章 音声がケーブルを伝わる
第4章 電波に声をのせる
第5章 テレビ放送時代の到来
第6章 コンピュータの誕生
第7章 地球を覆う神経網
第8章 IoE、ビッグデータ、そしてAI
エピローグ 「超」相克の時代を迎えて
著者等紹介
中野明[ナカノアキラ]
ノンフィクション作家。1962年、滋賀県生まれ。同志社大学理工学部情報システムデザイン学科非常勤講師。1996年に『日経MAC』誌上に短期連載した記事を『マック企画大全』(日経BP社)として出版した後、歴史・経済経営・情報の三分野で幅広く執筆する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
94
題名が「IT全史」とあるのですが、どちらかというと情報通信の歴史をわかりやすく通史として書かれている本だと思いました。この分野では松岡正剛さんの「情報の歴史を読む」というマニアックな本がありますが、それよりももう少しわかりやすいのではないかと思われます。「腕木通信」の時代から説き起こされていますが、私は「のろし」の方が古いのではないかと考えています。ただこのような分野の本はあまりないので参考になりました。2017/10/05
Kentaro
47
高性能コンピュータが電卓やパソコンをはるかにしのぐ能力を有していることに異論はない。実際、AIが統計学的に分析した結果を出力する能力には一目置かざるを得ない。しかしそれでもAIは万能ではない。AIは過去のデータにある相関関係を特定するものの、必ずしも因果関係までを明らかにするものではない。 AIをしても必ずや因果関係を突き止められるわけではない。突き止められるのは、統計的に見て「理由はわからないが両者には相関関係がある」という、機能法的結論である。2020/06/11
姉勤
35
約250年前のフランスで始まった腕木通信(三節棍のような木の組み合わせパターンで文字を示す)を情報技術の萌芽とし、電信、無線、テレビ、そしてインターネットと進化した人間のコミュニケーション。コンピュータとソフトウエアとネットワークの冪乗的に加速する進化は、情報を0と1の集合とし文字から画像映像と扱う情報が大きくなることで、人間かそれ以上の存在へと。技術知性:AIが今後どのような役割を担うのか。原理の発見や、発明した当事者が予想もつかない結果をもたらしたように、禍福は糾える縄の如し。2023/07/29
izw
10
腕木通信の発明がITの始めと考え、1893年から250年間、2044年までのITに関する歴史の俯瞰と20数年後までの方向性を論じている。シンギュラリティの2045年の前年までというのが洒落ている。腕木通信、電信、無線通信、ラジオ、テレビ、コンピュータ、インターネットまでを俯瞰し、IoE、ビッグデータ、AIが勃興している現在の状況から、未使用情報活用のトレンドを捉えている。利己主義と利他主義を超克するハイ・シナジーな社会となるかが課題である。非常に読みやすく、わかり易く、納得感が高い。2017/11/19
Yuichi Tomita
5
タイトルで損している。軽薄な「全史」や「大全」が跋扈しているように最近感じているので、その類かと思ったら、歴史を踏まえた上で考察がなされた本格的な内容だった。 腕木通信から始まり、無線、ラジオ、テレビ、インターネットと情報技術の歴史を説くと共に、そこから何か普遍的なもの、未来の予測に活かせるものを探っている。 歴史部分は正直知らないことだらけで、ドラマが面白い。インターネットの歴史よりもそれ以前の記載が多く、新鮮だった。2022/06/17