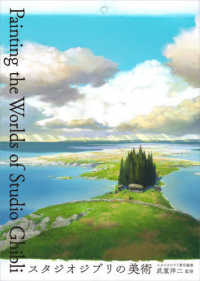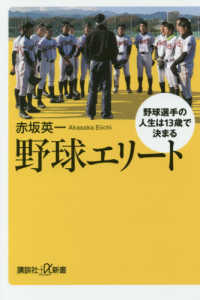内容説明
占いだけじゃない、愉しみ方。15世紀半ば、タロットカードの原型はイタリアの貴族社会で生まれた。当時は、貴族たちが絵柄に隠された神話や箴言などの「寓意」を読み解く、教養と想像力の試金石として使われていたという。以来、現代に至るまで世界各地で、その時々の社会情勢を反映しながら様々なタイプのカードが生まれてきた。本書は、東京タロット美術館が所蔵するカードの中から選りすぐりのものを取り上げ、図像に込められた意味を探るもの。大アルカナの0番「愚者」の成長物語として読み解く世界は、まさに人生の縮図でもある。神話や哲学、数秘術といった人類の叡智と出会いながら、自分の内面に目を向け「愚者」とともに成長してほしい。
目次
第1章 タロットは貴族の教養だった(発祥は、中世ヨーロッパ貴族社会;「タロット」と「トランプ」、どちらが先?;タロットの庶民化と「マルセイユ版」の誕生 ほか)
第2章 大アルカナと愚者の旅(愚者;魔術師;女教皇 ほか)
第3章 小アルカナの世界(「小アルカナ」と「トランプ」のルーツは同じ?;「棒」「聖杯」「剣」「金貨」…4種類のスートの意味とは;コートカードは何を意味するのか ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
榊原 香織
50
私が使ってたのはライダー版、まあ一般的ですね。黄金の夜明け団の系譜。 迫力あるのは20世紀最大の魔術師アレイスター・クロウリーのトート版、 新しいところで、画家サルバドール・ダリ版、漫画家魔夜峰央版、デビット・ボウイプロデュースのスターマン・タロットなど色々2023/03/18
Tatsuhito Matsuzaki
12
タロットの原型が確立された15世紀のイタリアから、18世紀の神秘主義との融合、19世紀の魔術結社による体系化、20世紀のユング心理学の影響などを経て、現代のリーディングや自己啓発ツールに至るまでの歴史を紹介。 続く2~3章では、「愚者」から「世界」までの大アルカナ22枚と、トランプとほぼ同じ構成&ルーツである小アルカナ56枚の意味を探ります。 本章のおわりに、最も簡単なタロットの使い方が掲載されていますが、カードが示すのはあくまで偶然の啓示であって、決して変えられない運命ではないとの説明には同感しました。2023/03/04
gokuri
3
読みかけの小説にタロットが出てきて、あらためてタロットの全貌を知りたくなり、図書館で入手。大アルカナの解説を通じて、0愚者から21世界までの解説を読むと、多くのカードは、その時の状況を多面的に解釈できるようになっている。図柄の美しや、版の違いによる奇妙さなど、なかなか奥深い世界を感じることができる。2023/06/06
ふゆきち
2
占いこそしませんが興味はあります。数秘術を核にした解説が分かりやすい。オールカラーで図番も豊富です。ニコレッタ・チェッコリ・タロットが気になりました。2023/11/13
アル
1
タロットについては漠然としか知らなかったので、概要をつかむための入門書として購入。 その意味では第1章のタロットの歴史解説が興味深い。 15世紀にゲーム用として生まれ、18世紀に神秘主義者に「発見」されたことで占いに使われていく流れや、マルセイユ版、ライダー版などの主要なデッキの位置づけがわかりやすく解説されていて、入門書として欲しい情報がコンパクトに纏まっている。 2章以降の各カード解説も、特に大アルカナは色々な種類のカードを上げることで一つの解釈にこだわらないようにしているようにも見えた。2025/02/02