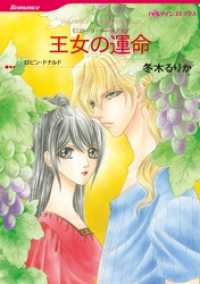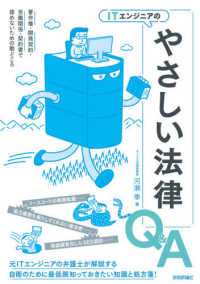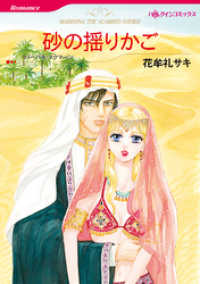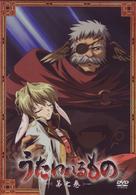内容説明
江戸には高札場が三十五カ所あった。そこに掲げられた御触書には、何が書かれていたのか?何が禁じられ、何が許されたのか?本書は一〇〇の御触書を解説し、そこから町奉行の政策と庶民の暮らしを考察したものである。為政者は禁令を乱発し、ほとぼりが冷めると人々はまた欲望のままに動き出す。その繰り返しから垣間見えるのは、お上と庶民の絶え間ない緊張関係だ。しかし、厳しいだけではない。災害が起これば救いの手を出し、凶悪犯捜査には懸賞金をつけた。非情と温情が交錯する御触書から、生々しい江戸の暮らしが甦る!
目次
第1章 自由と不自由―カタブツ幕府が躍起になった庶民の風俗・生活統制
第2章 珍事件・凶悪事件―治安管理にお上は大わらわ
第3章 災害救助―緊急事態!御触書が問う、時の幕府の真価
第4章 温情か、非情か―御触書に見る「庶民思い」と「庶民泣かせ」
第5章 旅の掟―まるで海外旅行!御触書が語る七面倒な旅事情
番外編 庶民にはわからない武士の世界―『武家諸法度』だけでない、御触書に見る武士の掟
著者等紹介
楠木誠一郎[クスノキセイイチロウ]
1960年、福岡県生まれ。大学卒業後、歴史雑誌編集者を経て作家となる。人気作家として多くの小説を上梓するとともに、題材を幅広く採った歴史関係の著作を数多く手がける(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。


![学園アイドルマスター 初星学園ステーショナリーセットBOOK [バラエティ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/42990/4299061055.jpg)