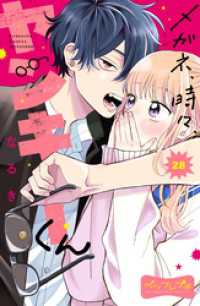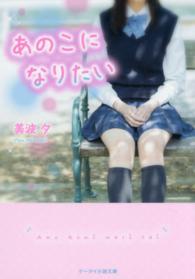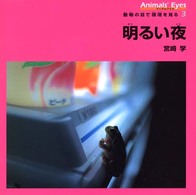内容説明
本書では、危機管理を専門とする著者が、東日本大震災、韓国のセウォル号事故などの最近の事例を分析・検証し、失敗の教訓の重要性を論じて個人および組織の危機管理の極意を説く。また、戊辰戦争・西南戦争などの幕末・明治の戦争、第二次世界大戦などの歴史的な事例も採り上げ、現代の組織にも通じる教訓へと落とし込んだ。危機管理の達人になるための必携の書。
目次
第1章 東日本大震災を振り返る
第2章 危機管理の極意
第3章 日本の安全保障
第4章 なぜ失敗の教訓を活かせないのか
第5章 歴史に学ぶ(幕末・明治編)
第6章 歴史に学ぶ(第二次世界大戦編)
著者等紹介
樋口晴彦[ヒグチハルヒコ]
1961年、広島県生まれ。東京大学経済学部卒業後、上級職として警察庁に勤務。愛知県警察本部警備部長、四国管区警察局首席監察官のほか、外務省情報調査局、内閣官房内閣安全保障室に出向。ペルー大使公邸人質事件、ナホトカ号重油流出事件、オウム真理教事件、東海大水害など様々な危機管理に従事。現在、警察大学校教授として、危機管理分野を担当。米国ダートマス大学MBA、博士(政策研究)。危機管理システム研究学会常任理事、失敗学会理事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
5 よういち
88
危機管理で重要なことを事例をもとに紹介。危機管理の本で紹介される原則は①正確な情報入手、②リーダーシップ、③危機管理マニュアルの整備。しかし、原則論だけでどうにかなるほど危機管理は甘くない。東日本大震災のとき、人間が考えた情報伝達の画期的な手段はほぼ壊滅させられたという。必要なのは「様々な要素を組み合わせて分析する知性と、具体的な対策を編み出していく概念能力、そしてバランスを持って全体損失を判断する大局観」だ。◆冷静に考えればデマには乗らない/コンプライアンスと危機管理は両立しない/自らの判断で行動する。2019/08/29
1.3manen
37
デマを信じてしまう人間心理(45頁~)。震災発生の特殊心理。不安感と調和する位悲劇的情報を受容する傾向にある。不安感からデマが発生する。デマは不可避。外交とはギブアンドテイク(125頁~)。トムラウシ山遭難のガイドは、ツアーごと、旅行会社側と契約を結ぶ契約ガイドで、仕事の割り当ては旅行会社に完全に依存(153頁)。家庭教師業界と似る構造か。判断ミスは、立場の弱さ、コミュニケーション不足、低体温症に対する知識不足。2015/10/31
K2
6
FaceBookに投稿されていた方のコメントから興味を持ち購読。 管理職なら必ず読むべき本ですね。 『危機管理』は、自分事化して初めて分かったことになることを再確認できました。2015/06/15
Mitz
5
福島第一原発事故、セウォル号沈没事故、トムラウシ山ツアー遭難事故など記憶に新しい出来事や、幕末・明治の内乱、第二次世界大戦中の戦闘を題材に、危機管理の要諦を説いている。著者は、“危機管理”という言葉は巷に溢れているが、今や原則論に偏った軽佻浮薄なものに堕していると憂慮している。この書では企業などの組織向けに警鐘を鳴らしているが、“危機管理”は、個人の生活とも無縁ではないだろう。むしろ、事の大小に関わらず、リスクを念頭においた準備・行動が必要であると、気が引き締まる思いである。なかなか読み応えのある良書だ。2015/07/04
丸太
4
面白かった。なかなか鋭い分析を見せる危機管理の本。特に前半は良かった。後半の歴史パートは意見が分かれそう。2017/11/04