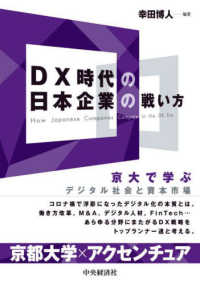内容説明
大倉集古館、大原美術館、根津美術館など、実業家の蒐集品を展示する人気美術館は多い。その一方で、設立の夢を果たせなかった美術館があったことをご存知だろうか。本書はそれを、「幻の美術館」と呼ぶ。紹介する五館は、質量ともに十分なコレクションを所蔵。蒐集した実業家たちも公開をめざしていた。頓挫した背景にはいかなる事情があったのか?夢が叶っていたら、どんな美術館になっていたのか?わずかに残されていた貴重な資料をたどり、その全貌を明らかにする。美術・歴史愛好家、垂涎の一冊!
目次
プロローグ(大倉喜八郎と大倉集古館;藤田伝三郎と藤田美術館;根津嘉一郎と根津美術館;「幻の美術館」に終わった人たち)
第1章 大茶人 益田孝と小田原掃雲台「鈍翁美術館」(三井の大番頭・益田孝;大茶人で希代の美術品収集家;井上馨との出会い ほか)
第2章 生糸王 原富太郎と横浜三之谷「三溪美術館」(古建築のテーマパーク;原家の入り婿;原商店から合名会社へ ほか)
第3章 造船王 川崎正蔵と神戸布引「川崎美術館」(高橋箒庵の神戸行き;川崎正蔵の鳴かず飛ばずの前半生;造船業ブームの波に乗る川崎正蔵 ほか)
第4章 勝負師 松方幸次郎と東京麻布「共楽美術館」(林権助の言葉;株式会社川崎造船所の初代社長に就任;第一次世界大戦の勃発と大造船ブーム ほか)
第5章 美術商 林忠正と東京銀座「近代西洋美術館」(希代の画商・林忠正;起立工商会社の臨時通訳としてパリへ;フランスで巻き起こった浮世絵ブーム ほか)
エピローグ(彼らの美術館はなぜ幻に終わったのか;幻の美術館に残る未練)
著者等紹介
中野明[ナカノアキラ]
ノンフィクション作家。1962年、滋賀県生まれ。同志社大学非常勤講師。歴史・経済・情報の三分野で執筆する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
なる
オサム兄ぃ
和草(にこぐさ)
abs862618
秋津