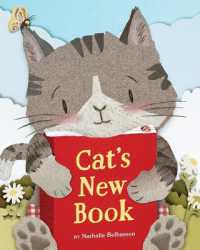内容説明
一期一会、自らを灯明とせよ、喫茶去、百尺の竿灯一歩を進む…など、禅のこころの根幹を現代人にやさしく伝える100の言葉。
目次
1章 空―不立文字(柳緑花紅―柳は緑 花は紅(蘇東坡)
子生而母危―子生れて母危うし(『菜根譚』) ほか)
2章 伝える―教外別伝(〓(そっ)啄同時―機を得て両者相応ずる得がたい好機(『碧巌録』)
語尽山雲海月情―語り尽す山雲海月の情(『碧巌録』) ほか)
3章 こころ―直指人心(天上天下唯我独尊(『五灯会元』)
大哉心乎―大いなる哉心乎(栄西禅師) ほか)
4章 知恵―見性成仏(自灯明―自らを灯明とせよ(釈尊)
燈下不截爪―燈下に爪を截らず(白隠禅師) ほか)
著者等紹介
松原泰道[マツバラタイドウ]
1907年(明治40年)東京生まれ。1931年(昭和6年)早稲田大学文学部卒。岐阜・瑞龍寺専門道場で修行。昭和26年臨済宗妙心寺派教学部長。昭和52年まで龍源寺住職。全国青少年教化協議会理事、「南無の会」会長等を歴任し、講演・著作に幅広く活躍。現代の「語り部」として、仏の教えを分かりやすく現代の言葉に置き換えて、噛み砕くように説き続けた。平成元年、第23回仏教伝道文化賞受賞。著書多数。平成21年逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぽんすけ
11
読むほどに仏の道は難しいと感じられる。書かれていることも求められていることも簡単そうでいて、本当に深淵で難しい。簡単そうに見えることが本当は酷く困難であることは実生活でもあるが、仏の道は一見平坦な道に見え歩き始めるとどんな峻険な山道より険しい。「両忘」…豊かさと貧しさ、生と死とを対比するから楽と苦の両方が生ずる。生きるとは精一杯生き。死なねばならぬ時は大いなるものに任せきる。その時生死は事実にして生死に振り回されない自由が得られる。すごく印象に残った部分。この本は何度も読むべきものだと思う。2024/10/04
すーさん
4
「両忘」という言葉を偶然知り、禅ってすごいと思い興味を持った。「両忘」とは、上手い下手、勝ち負けなど対立する概念を超えるという事。上手いか下手かなんてどうでもいいと思わせる絵や歌、勝ち負けを超えた素晴らしい試合など。確かにそういうものはあるし、心を掴まれるのはそういうものに触れた時だ。禅問答というと、難解でわけわからんものの例えに使われるが、確かにある真実が垣間見えるような気がする。2023/03/07
よし
4
「一期一会」「自らを灯明とせよ」「百尺の竿頭一歩を進む」……など有名な語も多い。「禅とは、釈尊のさとられたこころを伝えるものであり、その禅のこころを文字で表わしたのが「禅語」である。」とある。読んでいる間、心の緊張がとれ、俗世間の煩わしさから逃れることができた。付箋紙で一杯になった。セレトニン が一杯出たベスト5をあげる。「ー日作さざれば ー日食わず」「脚下を看よ」「日々是好日」「心痛はしてはならぬ。が、心配(心を配る)は大いにせよ。」「新婦 驢に騎れば 阿家あこ牽く」 2017/10/07
狐狸窟彦兵衛
4
昭和47年(1972年)に出版された本を新書化したものだそうです。千年以上も前の言葉を集めている、40年前の本ですが、「古さ」は感じません。「喫茶去」(お茶でも召し上がれ)「看脚下」(足元をよく見よ)など日常会話のような言葉に、深い知恵が込められていることがよく分かります。茶室の床にかかっている禅語がどんな場面で語られたのかが解説してあり興味深かった。「燈下不截爪」(灯りの下で爪を切るな)という、迷信めいた忠告まで意味に奥行を与えていることなど、「禅」というものが、生活にもっと近い存在だと感じました。2012/12/04
読書家さん#ppCoIY
1
禅語の臨済宗的な解釈を学べる2024/09/26
-
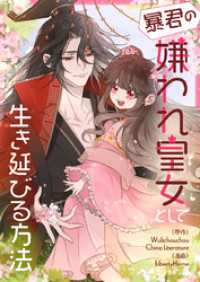
- 電子書籍
- 暴君の嫌われ皇女として生き延びる方法【…