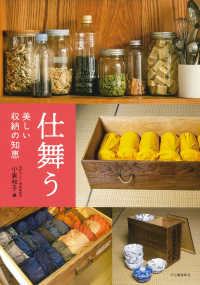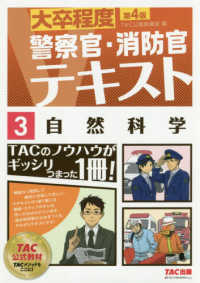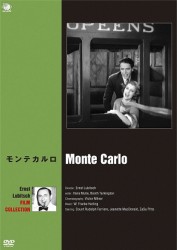内容説明
西郷隆盛、佐久間象山、吉田松陰、坂本龍馬―彼らはなぜ、この本に心酔したのか。仕事、人づきあい、リーダーの条件…変わることのない人生の指針がここにある。
目次
序章 現代こそ『言志四録』が役に立つ(論語ブームと『言志四録』;心に響く「短い言葉」 ほか)
第1章 「忙しい」の九割は無駄な仕事―仕事術(事前によく考えれば、スムーズに進む;仕事はまず解決可能性と優先順位を判断する ほか)
第2章 禍は「上」から起こる―人間関係・リーダー論(第一印象は間違いない;人間を座標軸で捉える ほか)
第3章 志がれば、何からでも学べる―学習法(人生はいつでも学ぶべきときである―「三学の教え」;師をどう選べばよいか ほか)
第4章 「やむを得ざる」の生き方―人生論(「やむを得ない」のが本物だ;夢を見るのではなく、夢に見ろ ほか)
著者等紹介
齋藤孝[サイトウタカシ]
明治大学文学部教授。1960年、静岡県生まれ。東京大学法学部卒業。東京大学大学院教育学研究科博士課程等を経て現職。専門は教育学、身体論、コミュニケーション論。小学生向けセミナー「斎藤メソッド」主宰(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うりぼう
98
「言志四録」という書物の存在を知らず、当然、佐藤一斎という人物も。同じ言葉でも漢文になると響が違い、身が引き締まる。斎藤氏は、判り易く本を書くことにおいて、田坂広志氏と双璧と思う。田坂氏の方が詩的。斎藤氏の想いが、引用文の選択に顕れる。ポストモダン以後の迷える大人達に指針をとの気概。要はバランス、中庸であり、自分と自然、心と身体である。「思う」とは「工夫」すること。「才」を捨てて「量」を取らん。「志」立てば、全てに学ぶ。只、「一燈」を頼め。西郷どんと斉藤氏の違いは、時代の差か?西郷どん、晩・耋からを好む。2010/12/24
ehirano1
73
再読。本書に書いてあるとおり、「言志四録」はどれもそれほど目新らしいものではないのですが、最も重視されているのはオリジナリティではなく、”それが本当に役に立つ言葉なのかどうか(p55)”が強く印象に残りました。では、当方にとって本書から本当に役に立つものは何であったか(何を掴んだか)?それは、”克己は工夫である(p86)”ということでした。2016/05/03
月讀命
60
『少にして学べば、則ち壮にして為すことあり。壮にして学べば、則ち老いて衰えず 。老いて学べば、則ち死して朽ちず』人間は生きるにつけ、何時でも勉強が必要であり、勉強する事で人間性が向上するのではないでしょうか。この本を読むまで、佐藤一斎の残した『言志四録』について全く知り得ませんでした。斎藤孝先生が『最強の人生指南書』と謂うだけあって、迷った時、苦しい時、方向性を見失った時、今後の人生の羅針盤になりえる座右の銘と云えましょう。今後「言志四録」の原作をじっくりと噛み砕きながらページを捲ってみたいものですね。2012/06/10
こーた
27
コロナで社会が不安定なせいか、こういった教訓を読みたくなります。2020/05/10
リョウ万代ホーム施主|貯金おじさん
24
何回も読み直したい内容です。2016/01/06