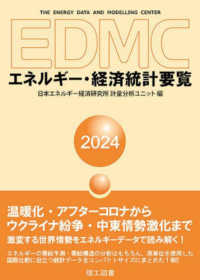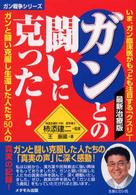目次
1 小布施まちづくり研究所研究報告(主体と地平の形成を目指す思考実験の歩み―身体を触発し、日々の体験に問い続ける;国道403号整備の意匠計画;照明計画―生活の光の利用;里道―道のネットワークと拠点づくり ほか)
2 小布施まちづくり大学ワークショップ(小布施まちづくり大学ワークショップ;横浜国立大学Y‐GSA/刻々とめぐる;東京理科大学+コロンビア大学スタジオX/Neighborhood of Light;東京芸術大学/小布施サンプリング ほか)
著者等紹介
川向正人[カワムカイマサト]
小布施まちづくり研究所長、東京理科大学理工学部建築学科教授。1950年、香川県生まれ。1974年、東京大学建築学科卒業、同大学大学院進学。1977‐79年、政府給費生としてウィーン大学美術史研究所・ウィーン工科大学に留学。明治大学助手、東北工業大学助教授を経て、1993年、東京理科大学理工学部建築学科助教授。2002年‐、同教授。2005年‐、東京理科大学・小布施町まちづくり研究所長兼務(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
17
人口でいえば僕の合併後の町よりも人口が少ないのに、かくも魅力あふれるまちができているのか? その秘訣を余すところなく開陳している一冊。白線駐車線ではなく、樹影のパターンが地面に描かれている(022頁)。これなら景観として違和感がない。左頁日本語、右英語の構成が基本となっている。水車のある風景はまちづくりの基本だとも思われる。随所に他地域でも参考に資する景観整備のアイデアが活かせると思われる。落差が2.5メートルもあれば水車として機能するようだ(047頁)。 2014/12/23
葉
0
照明計画や意匠計画について序盤は書かれている。まちと大学の共存が多く書かれていると思っていたが、大学からまちへのアプローチとして、10未満の大学のやり方について書かれているだけだった。大阪市大は空き家をセミナールームとして使っているらさい。ここには書かれていないが、奈良県立大学は学外授業として、奈良のまちの活性化アプローチのような授業がある。神戸大学ではごみジャパンという環境経済学の学外授業のようなものがあるらしい。2015/02/09
もりした
0
まちづくりについては全くの無知やけれど、多くの人の関わりでまちが良くなっていく様はとても素敵だなぁと思えた。学生からのまちづくりの提案も、一つのまちに対して色々なアプローチがあって面白い。いつか小布施町行ってみたいなぁ2018/02/02
-

- 電子書籍
- ×××HOLiC(18)
-

- 和書
- 教授の発達論的構成