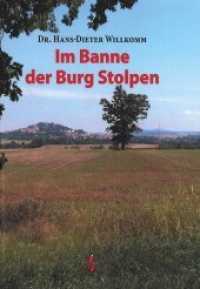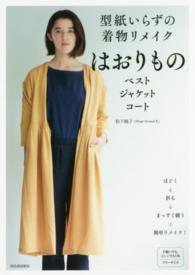内容説明
中学・高校の18科目から、建築の面白さを体験してみよう。
目次
数学「幾何学を開放する」
生物「建築は、もっと自然に近づくことができる」
美術「つくること、みること、かんがえること」
英語「建築も英語も、コミュニケーションがものをいう」
政治経済「建築を動かす社会の仕組み」
情報「あらかじめ、つくり方をつくる」
算数「小数点がない時代、建築はどうつくられてきたか」
国語「建築と言葉は切っても切れない」
家庭「住み手の視線で建築を考える」
化学「私たちはマテリアル・ワールドに生きている」
課外授業「物語を紡ぎ、空間を形づくる」
倫理「分からないものへの憧れ」
体育「次世代の建築家に求められる運動能力」
歴史「教科書にのる建物」
物理「安全と豊かな空間を生み出す構造」
地理「風土と建築の新しい関係」
音楽「聞こえない音と見えない空間を読む」
修学旅行「旅に出ることは、建築と出会うこと」
著者等紹介
五十嵐太郎[イガラシタロウ]
1967年、フランス・パリ生まれ。1990年、東京大学工学部建築学科卒業。1992年、東京大学大学院修士課程修了。博士(工学)。2008年、ヴェネチアビエンナーレ国際建築展日本館コミッショナー。2013年、あいちトリエンナーレ芸術監督。平成25年度文化庁芸術選奨文部科学大臣新人賞。現在、東北大学大学院工学系研究科都市・建築学専攻教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
紫羊
21
14歳の甥は建築家という職業に関心があるらしい。プレゼントするのにぴったりの本を見つけたが、例によって先に読んでしまった。建築家を目指すにあたって、中学や高校で学ぶ全ての教科、果ては修学旅行まで、ひとつとして無駄なものはないのだということが良く理解できた。わかりやすく、おもしろかった。2017/01/21
nbhd
8
世に蔓延っている「モダンなかんじがステキ!」の基本は、1932年にニューヨーク近代美術館で開催された「モダン・アーキテクチュア展」に発するとされている。(1)「量塊(マス)」ではなく「面に包まれたボリューム」としての建築。(2)軸線によるシンメトリーとは異なる方法で秩序づけられた「規則性」の希求。(3)「装飾不可の忌避」。2017/09/05
Sato
6
建築の専門家がいろいろなジャンルと建築をからめ興味深く建築の世界へ誘う。「建築を知ると旅が楽しくなる」なるほど。2015/06/29
前田まさき|採用プロデューサー
4
本書は、中学・高校で学ぶ授業の枠組にあてはめながら、建築のおもしろさを紹介したものである。古代ローマのウィトルウィウスは、建築家たるものは文章術、描画法、幾何学、光学、算数、歴史、哲学、音楽、医学、法律、天文学など多様な知識が必要だと述べたが、現代においても基本的にその前提は変わることがない。(p.2)。2019/12/07
ざっきい
4
ふと目につき読んだ本。建築学入門的なものを想像していたため肩透かしではあったが、建築を政治経済、化学、歴史、地理などと絡めて語ろうというコンセプトは面白かった。混淆としている所もあるが、平易な語り口であるため14歳なら面白いかもしれない。2017/02/05
-
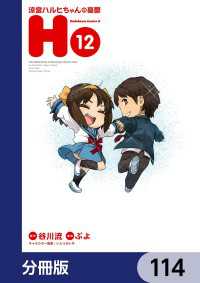
- 電子書籍
- 涼宮ハルヒちゃんの憂鬱【分冊版】 11…