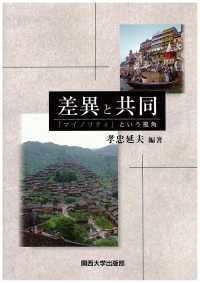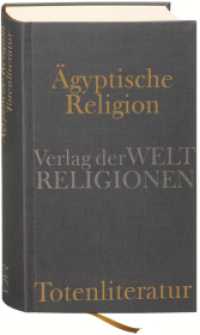内容説明
「ナショナルなものとは、現在および各時代ごとの共通分母の横糸と、全歴史を貫く縦糸とが、織りなすものをいうのではなかろうか。そしてその中に存在するメカニズムを分析することによって、初めて国民的な広がりをとらえることも可能となろう。」―日本から世界に発信した唯一の建築ムーブメント「メタボリズム」の提唱者は、こんなにも「日本」と「伝統」について考え抜いていた。
目次
1 美の意識と構造(生きているカタチ;風―予感の美学;竹―東洋の象徴;暮らしの中の美)
2 カタチ論
3 建築と庭園(伊勢神宮の造形―伝統論の出発と終結;薬師寺の東塔;西芳寺の庭園;桂と日光)
4 国民文化論(国民的秩序の形成;国民文化の形成;国民文化論の盲点;国際交流と国民的伝統)
著者等紹介
川添登[カワゾエノボル]
1926年、東京生まれ。建築、都市評論家。早稲田大学文学部心理学科を経て、同大理工学部建築学科を卒業。1953‐57年『新建築』編集長。かたわら、「岩田知夫」のペンネームで建築評論を執筆。1960年、「メタボリズム」に参加。いわゆる「伝統論争」を仕掛け、建築評論の礎を築く。1968年、梅棹忠夫・加藤秀俊・小松左京・栄久庵憲司らと「日本未来学会」発足。1970年、「CDI/コミュニケーションデザイン研究所」設立。1972年、「日本生活学会」創設(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 「死ぬ瞬間」と臨死体験