内容説明
本書は、現在の日本の大学、工業高校および専門学校の建築学科で行われている建築構造の教育に使われるテキストとして作られた。すべての学生に「構造の専門家になるための初歩」を教えようとする教材としてではなく、「これから建築を学ぼうとする人」を読者に想定し、構造の専門家でなくても、つまり「構造の専門家にならない人」でも、「このくらいは心得ておきたい」領域に内容をしぼって、広く浅く、そして楽しみながら建築の構造を理解していただけるように、このテキストはさまざまな工夫をこらして構成されている。
目次
1 建築の構造システム
2 木材系の構造システム
3 コンクリート系の構造システム
4 鋼材系の構造システム
5 膜材系の構造システム
6 建物を支える構造システム
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Haruki
4
建築材として、木材、コンクリート、鋼材、膜材に分類。部材幾何構造として、直線材、平面材、トラス構造、湾曲構造、ケーブル吊り構造、張力膜に分類。力の種類として、引張、圧縮、せん断、捩れ、曲げモーメント、力の流れ、座屈を見ながら、その制御構造として、素材特性、アーチ形、シェル型、ラーメン構造(節点のリジット接合)、トラス構造(三角形=非変形)、懸垂線(引張力のみ)に分類。これらを踏まえつつ建築物の大きさ、内部空間、耐震性、作りやすさ、コスト等を満たす適切な構造システムが適用される。図説で幾何的な理解もできる。2024/03/23
よこ
0
興味があったので読みました。 どうして建物は安心して暮らせるのだろう。 どうして簡単に崩壊せず、そこにあり続けるのだろう。 という疑問をもちました。2018/04/05
-
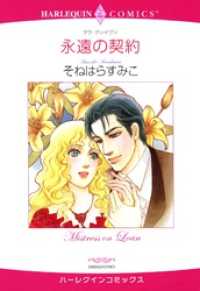
- 電子書籍
- 永遠の契約【分冊】 2巻 ハーレクイン…
-

- 電子書籍
- 異世界のんびり農家(2) ドラゴンコミ…
-
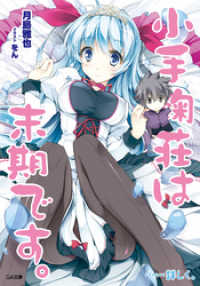
- 電子書籍
- 小手鞠荘は末期です。……詳しく。 GA…
-
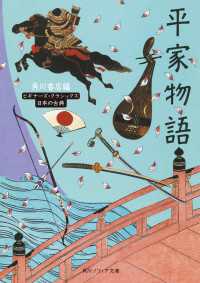
- 電子書籍
- 平家物語 ビギナーズ・クラシックス 日…





