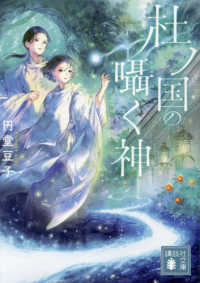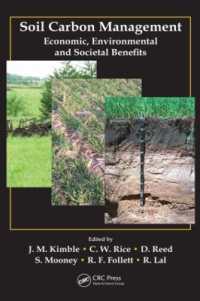目次
第1章 ケアする人に必要な「寄りそう」力(「癒す」ということの意味;ホスピスの基本は「親切なおもてなし」;ホスピスの由来 ほか)
第2章 ケアする人に必要な「人間力」(ミルトン・メイヤロフが語る「ケアの本質」;ケアする人の持つべき資質とは;末期患者とのコミュニケーション ほか)
第3章 ケアする人に必要な「ことば」(『死にゆく人々のケア』;「私の希望は、ホスピスがこの世からなくなること」;“Not doing,but being” ほか)
著者等紹介
柏木哲夫[カシワギテツオ]
1965年大阪大学医学部卒業。同大学精神神経科に勤務したのち、米ワシントン大学に留学し、アメリカ精神医学の研修を積む。72年に帰国後、淀川キリスト教病院に精神神経科を開設。日本初のホスピスプログラムをスタート。93年大阪大学人間科学部教授に就任。退官後は金城学院大学学長、淀川キリスト教病院理事長を歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
57
日本のホスピスの先駆者である淀川キリスト教病院の柏木哲夫先生のご講演をまとめた一冊。精神科医の柏木先生が、ホスピスの母であるソンダース先生のところで学び、「ホスピス医は身体をしっかり診れることが大切」だと悟って、帰国後、自ら申し出て内科の研修医の修業を積んだ話が印象に残る。奉仕の精神とか慈愛の心などの精神論ではなく、ホスピスとしての能力や技術に多く言及されているが、それこそプロだと納得する。「支えるではなく寄りそう」「doingではなくbeing」「集める人生より散らす人生」など素敵な言葉にも出会う。2020/08/05
たっちゃん
0
・ホスピスのこころとは、弱さに仕えるこころ ・気持ちを分かってもらえる安堵感 ・「励ます」、「支える」、「寄り添う」の違い ・支えるは技術の提供、寄り添うは人間力の提供 ・痛みや症状のコントロールしか目を向けない「ホスピスの医学化」を危惧する ・4つのケア①身体的ケア②心のケア③社会的ケア④魂のケア ・大切なことは、患者のそばにきちんと存在すること ・最後の数時間に起こったことが、残された家族にとっては、心の癒しにも回復の妨げにもなる ・矢先症候群 ・引っ張り症候群 2025/05/03
-

- 電子書籍
- ビッグコミックオリジナル 2021年1…