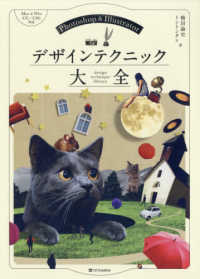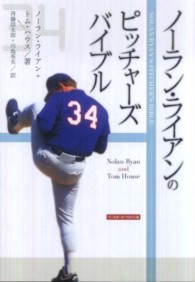内容説明
「日本の食はすごい」説は、どこから来たのか?舶来モノに目がなかった日本人が、「国産」をありがたがる時代。一体、何が起きているのか?地産地消ブームから貿易政策まで、メイド・イン・ジャパンの威光を放つ物事の“本当のところ、どうなのか”を徹底検証。知っているようで知らない食卓の歴史。
目次
“国産”のブランド力
“トレンド”としての地産地消
「食えるものは食え」のこころ―明治から太平洋戦争まで
食生活の五五年体制
食糧危機ふたたび!?大豆ショックとオイルショック
添加物恨み節
一人歩きした日本食礼賛
バブルの後にやってきた黒船―牛肉・米の市場開放
空前絶後の粗食ブーム
集団食中毒二〇年史
狂牛病パニック―地に堕ちた食の安全と国産信仰
あぁ、食料自給率
著者等紹介
畑中三応子[ハタナカミオコ]
1958年生まれ。編集者・食文化研究家。編集プロダクション「オフィスSNOW」代表。『シェフ・シリーズ』と『暮しの設計』(ともに中央公論新社)編集長を経て、プロ向けの専門技術書から超初心者向けのレシピブックまで幅広く料理本を手掛け、近現代の流行食を研究・執筆。第3回「食生活ジャーナリスト大賞」ジャーナリズム部門の大賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ようはん
17
近代の食文化史の中で平成の米騒動やBSE騒動、雪印の食中毒事件など記憶に残る事件も多い。しかし改めて日本は食料の自給率は低い。ここ近年の国際情勢の悪化でどうなっていくのであろうか。2024/06/07
みなみ
12
明治以降の日本の食の変遷を追いかける一冊。白米のごはんに執着を見せる日本社会だが、戦前から米をずっと輸入していて(当時植民地だった台湾や朝鮮からは移入としてカウントされた)国産米信仰がありながらも米の消費量は減り続けている。戦後アメリカの余剰食料を輸入したことから始まった小麦食、違法状態の食品添加物、牛肉オレンジ自由化やBSEと年代により起る食の問題を取り上げる。BSEに対する危機管理の無さと初動の遅さは新型コロナでも見られる日本の官僚組織の致命的な欠陥だと感じる。2022/03/17
白黒豆黄昏ぞんび
8
戦争なんて2度とするべきじゃないと思いますよ。配給の時代も、お上だけいいもの食ってたんじゃないかと疑ってしまうね。2024/01/24
にこまる
5
なかなか興味深い。近代〜現代の食文化史。政治的な背景にも触れつつ、わかりやすく書かれている。日本はなぜ食料自給率が低いのかが、ざっくりとわかって良かった。なんだか見かける「マクガバン・レポート」は実は日本食(和食)をほめてない、触れてもいない、かなり歪曲されて日本では紹介されていたことにビックリ!自分で元ネタを調べることの大切さを改めて実感した。無添加信仰、国産信仰もこんな流れがあったためなのか‥食品に対する衛生管理や基礎知識、下拵えの大切さを再認識した。2021/11/13
ganesha
4
食文化研究家の編集者による日本の食について幅広く書かれた1冊。明治から戦中・戦後の食料事情や輸入、食糧難や添加物、O157や狂牛病など、なかなかヘビーな内容を興味深く読了。2020/09/03
-

- 電子書籍
- 魔王軍最強の魔術師は人間だった(コミッ…
-
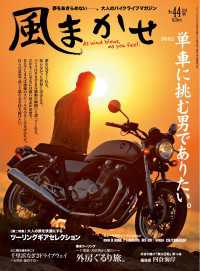
- 電子書籍
- 風まかせ (No.44)