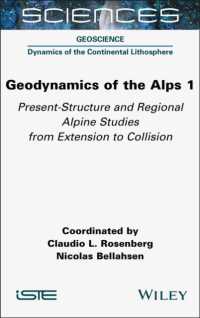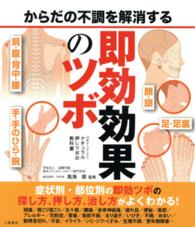内容説明
手塚をマンガ家として“復活”させたもの―それは、オキナワだった。戦争、基地、アメリカ、「ハーフ」のヒロイン、海と島…。その描写にこめたものは何だったのか。オキナワ、そしてその先へと広がる「水平線の思想」とは。かつてない手塚論にして、出色の戦後日本考。
目次
はじめに 「海の未来」、アクアポリス、そして手塚マンガ
第1章 「顔」と「身体」の表象
第2章 「南」への欲望―「少年」「孤児」「南の島」
第3章 「野蛮」のエロティシズム
第4章 「戦後日本」とアメリカ
第5章 地図の欲望―「島」と「海」
第6章 すべては物語のために―手塚が手にした神の視点
無意識と意識の「手塚治虫」―おわりにかえて
著者等紹介
本浜秀彦[モトハマヒデヒコ]
1962年那覇市生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。川崎製鉄(現JFE)勤務、琉球新報記者を経て、ペンシルベニア大学大学院博士課程修了(Ph.D.)。現在、沖縄キリスト教学院大学准教授(比較文学、メディア表象論)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゴーヤーチャンプルー
9
漫画をあまり読まなっか事もあり、手塚治虫作品は全く読んでない。なので、ちょっと頭に入りにくい感じではあった。戦争を生き抜いた手塚治虫は1970年代の沖縄の「本土復帰」と、「海洋博・アクアポリスの展示プロデューサー」という経験から、オキナワを舞台にしたマンガ作品を4本書き残していた事を知った。米軍基地、朝鮮戦争、ベトナム戦争、核開発、米軍兵による女性への蛮行などと言ったアメリカへの痛烈な批判。そして沖縄の土地開発と環境破壊、生態系への懸念、様々なメッセージが書かれているという。読んでみよう。2025/09/30
Hiroki Nishizumi
3
面白かった。手塚治虫が海洋博のプロデューサーをやっていたことは知らなかった。また手塚治虫は繰り返し島を描いているが、それは常に島の外からの視線であり、本土の意思表示を示唆しているとの指摘も興味深い。熱烈なファン故の消化不良も感じるが、現代を見つめる指標として、さらに深い発表を待ちたい。2018/05/12
きいち
3
「島」「南」というテーマに特化した手塚治虫論。「海の姉弟」にせよ「イエローダスト」にせよこのテーマでなければ取り上げられないし、確かに他の作家と比べても、特に初期、島モノの率は高い。「島」を物語を動かす舞台として活用できたことは、物語表現を上達させる上で大きな意義を持っていたということだ。そして、南洋ロマンの題材としての南の島から、戦争と環境問題の焦点としてのオキナワへの変化。このテーマへの思いの強いという著者ならではの掘り下げになっていて、よかった。もっともっと我をだしてもらったら、さらにいいと思う。2012/03/25
まんだよつお
1
手塚マンガと沖縄の現代史とをむりやりくっつけたという感じ。これでは沖縄について語った本なのか、手塚マンガを語った本なのか、中途半端。両者に関してはそれこそ多くの先人たちの研究成果が発表されている。こうした中途半端なスタンスで論じることは、先人に対して、また何より手塚と沖縄に対して失礼千万である。2011/01/14
aur0ra
1
寄る辺を失った、おぼろげな戦後日本が高度成長を遂げる過程で見失ってきたものを、手塚作品から丹念に拾い上げようとした好著。マンガの神様は「境界」を描き、オキナワは日本と米国の「境界」となる。その二つの出会いによって、日本だけでなく、人間が本来的に抱える危うさを浮き彫りにする。2010/09/27