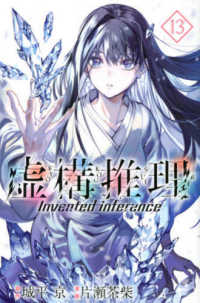内容説明
時間の厚みを生きる。階段のおり方、痛みとのつきあい方…。「その人のその体らしさ」はいかに育まれるのか。障害をもつ人の11のエピソードをもとに、体に蓄積する記憶と知恵を考察。
目次
メモをとる全盲の女性
封印された色
器用が機能を補う
痛くないけど痛い脚
後天的な耳
幻肢と義肢のあいだ
左手の記憶を持たない右手
「通電」の懐かしさ
分有される痛み
吃音のフラッシュバック
私を楽しみ直す
著者等紹介
伊藤亜紗[イトウアサ]
東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教授。マサチューセッツ工科大学(MIT)客員研究員。専門は美学、現代アート。もともと生物学者を目指していたが、大学3年次より文転。東京大学大学院人文社会系研究科美学芸術学専門分野博士課程修了(文学博士)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
鉄之助
285
人体の不思議! を感じさせてくれる1冊だった。事故で失った左足が、右足より「器用」になったと言うダンサーの大前光市さんに驚いた。義足をはめ、かばうようにして使っていた左足を「元々あるものとして」踊るようになったら「足の再発見」。そしたら、利き足も右から失った左に変化したとも言う。この本を読んで新鮮だったのが、著者の「個性的な表現」だった。「全力でメモを取る全盲の女性」「痛くないけど痛い脚」…。障害を持つ12人にインタビューした11のケースそれぞれが味わい深かった。2024/08/15
どんぐり
107
障害者の身体論をテーマにユニークな研究をしている伊藤さんの本。視覚障害、四肢切断、麻痺、吃音、難病、二分脊椎症など障害のある人のからだに刻まれた記憶と自身のからだを使いこなす11人のエピソードが紹介されている。メモを取る中途障害の全盲の女性、点字の数字と文字を読むときに頭の中で色をイメージするエンジニア、VR利用の体験で幻肢痛を緩和する人など、自己のからだとの応答で獲得した身体的体験の語りは目からウロコである。→2021/05/30
アキ
86
11人の障害をもつ人たちへのインタビュー集。どのケースも面白い。エピソード1全盲なのに話しながらメモをとり、アンダーラインを引く女性。2点字をする際に数字や文字とともに色が見える。5全盲の読書家の読書体験の仕方。体験からの体の記憶に規定されている身体は、失って初めて意識化される。「オートマからマニュアルへ」変わった感じ。この11人はみんな、身体を多重化させることで、環境と自分をつなぎ合わせ、更には社会と自分をつなぎ合わせている。そして全員そんな障害は消失して欲しいとは決して言わない。身体と記憶の深い関係。2020/01/22
たま
66
『体はゆく』に続いてこちらを読む。身体の圧倒的な固有性に迫る、という前書きどおり、障がいのある人たちの障がいの固有性やその記憶が克明に記される。身近な人を見ていても、同じ病名でも病状は実に人さまざまだし、身体の記憶という点で言えば、普通の人が老化とともに数年前にできたことができなくなっているのにそれを自覚できないケースは幾らでも目にしている。そんなことを思いながら、伊藤さんの実に綿密な記述と分析を面白く読んだ。2023/07/15
おさむ
44
障害者や吃音者らへの聞き取り研究で知られる伊藤さん。本著はそうした人達の身体らしさと記憶の関係について掘り下げている。当事者しか語れない言葉があり、それを万人に理解できるレベルで言語化するのが、伊藤さんの文章力。とりわけ中途障害者達の語る感覚は、もし同じ状況になったらと想像でき、わかる気もした。ヒトは「記憶」のおかげで生きているとまでは言わないが、健常者以上に障害者にとって記憶は、大切なんだなと思いました。2019/11/03
-

- 電子書籍
- レアモンスター?それ、ただの害虫ですよ…