- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 哲学・思想
- > 日本の哲学・思想一般(事典・概論)
内容説明
日本人は“死”と“死後”をどのように生きてきたか。“生”と“死”を見据え、“魂”を見据えてきた日本人の心を、「おのずから」と「みずから」の「あわい」のうちに、鮮烈に描く刮目の日本思想論。
目次
1 「おのずから」と「みずから」の「あわい」で―魂論の現在まで(死後の魂をどう考えたらいいのか;魂の感じ方・問い方 ほか)
2 「人間の霊的生命はかくも無意義のものではない」―西田幾多郎の哲学の理由(「生きるかなしみ」;愚痴と人情 ほか)
3 「余は必ず些かの嘘なき大往生の形を示さん」―国木田独歩の臨終祈祷拒否(「余は祈ること能はず」;未決の「霊性問題」 ほか)
4 「私か、私も多分祈れまい」―正宗白鳥の臨終帰依(「私か、私も多分祈れまい」;「つまらない」という思想・無思想の感受性 ほか)
5 「死は前よりしも来らず、かねて後に迫れり」―『徒然草』の無常理解(「死は前よりしも来らず、かねて後に迫れり」;「つれづれ」ということ ほか)
著者等紹介
竹内整一[タケウチセイイチ]
1946年、長野県に生まれる。東京大学文学部倫理学科卒業。専修大学、東京大学教授などをへて、現在、鎌倉女子大学教授、東京大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tamami
6
著者は、東京大学の倫理学の教授。肩書きだけで敬遠されそうであるが、私は何年に一冊というくらいのペースで刊行される著者の本に一人対面しては、今自分が、列島の時空を超越する形で、古今の人々とつながっていることを感じ、微かな安寧を得ているといった次第。今回の「魂と無常」というテーマは、自分などにはより直接的に響いてくる内容だけに身近に感じることができた。わが国の歴史上では生死一つにしても先人・偉人による様々な捉え方がある中で、日々何を齷齪、といった思いにも浸らせてくれ、心の安らぎを与えてくれる。2020/02/10
Go Extreme
1
近代的・合理的考え方→偏見or錯覚 釈迦・無記:形而上学的な問題には答えず 魂:その人たらしめるもっとも大事な何ものか+超えでて働く・越えたところから働いてくる何ものか⇒吉田松陰・誠 日本人の感じ方:おのずからとみずからのあわい→両者が働き合う 哲学の動機:驚き<深い人生の悲哀=生きる人間の自己矛盾 かなしみ:天地悠々の哀感・同情の哀感 至誠にして動かざる者は、いまだこれにあらざるなり 死は前よりしも来たらず、かねて後に迫れり 心を安くしておく=さながら心=柔軟真→つれづれ 道元:而今を自在に生きる2020/02/15
-

- 電子書籍
- 固有スキル「奴隷図鑑」【単話版】(52…
-
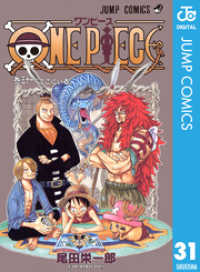
- 電子書籍
- ONE PIECE モノクロ版 31 …







