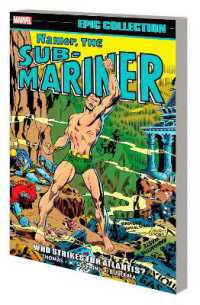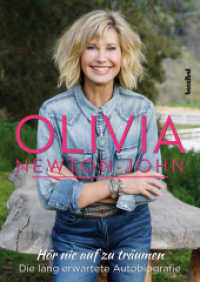内容説明
霊性的直観に導く「金剛経の禅」と、宗教とは何かを問う「禅への道」。禅思想の根源へと読者をいざなう名著!
目次
1 誤解の二、三
2 宗教とは何か?
3 矛盾・悩みの禅的解消法
4 禅は究竟の「人格」を見る
5 趙州の三転語
6 生と死
7 至善にとどまる禅
8 誓願行の禅
9 禅経験の学的説明について
著者等紹介
鈴木大拙[スズキダイセツ]
1870年石川県に生まれる。本名、貞太郎。円覚寺に参禅し、円覚寺派管長である今北洪川、釈宗演に師事し、大拙という居士号を受ける。1897年釈宗演の縁により渡米し、雑誌編集に携わる。1909年に帰国後は学習院、東京帝国大学、真宗大谷大学に勤務。英文著作も多く、ロンドンでの世界信仰会議やエラノス会議へ出席するなど、広く欧米に仏教を紹介した。1966年死去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
5
「即非の論理」(「Aは非AだからAである」)は『金剛般若経』13節の「仏説般若波羅 即非般若波羅蜜 是名般若波羅蜜」に由来する。この論理は「山は山でない、ゆえに山は山である」と例示可能だが、悟りという宗教体験を通した点に注目すべきだろう。この論理は、その根底にある「山は自己であり、自己は山である」という無分節の実在の直覚の効果、と考えられるからだ。意味に囚われた言語からなる日常から無意味を引き出す禅問答が、言葉遊び的なノンセンスと異なるのは、この問答が言語世界を離れる悟りへ向けた禅行為の一環だからである。2021/03/19