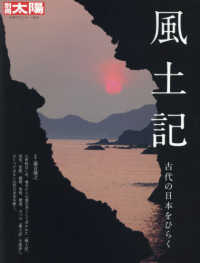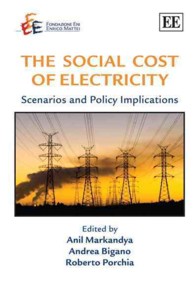出版社内容情報
体験の宗教・仏教、その瞑想の具体的なあり方を語る。東アジア世界の瞑想修行と、現代アジアに展開する現在の瞑想の姿を描く。
内容説明
仏教の「瞑想」とは、どのようなものか。知られざる瞑想の内実を明らかに示し、仏教の「悟り」と「救い」にいたる道を明かす。
目次
第1章 仏教瞑想とはなにか―サマタとヴィパッサナー(輪廻思想;輪廻の根源は心の働き ほか)
第2章 東アジア世界の仏教瞑想(中国への仏教の伝播;仏典翻訳の時代 ほか)
第3章 日本における瞑想修行(日本仏教の特徴;南都の伝統 ほか)
第4章 現代アジアの瞑想の実際(ミャンマーにおける瞑想;マハシーの実践 ほか)
著者等紹介
蓑輪顕量[ミノワケンリョウ]
1960年、千葉県に生まれる。1983年、東京大学文学部卒。1998年、博士(文学)。現在、愛知学院大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件