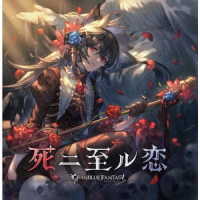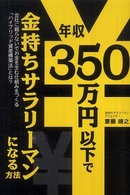出版社内容情報
中央アジアの仏像や仏画を通して仏教美術の意味を「仏教思想と信仰」「社会と政治」「異文化と異宗教」という三つの視点から読解。インド西北部のガンダーラやバーミヤーン、中国西域の敦煌・トルファンなどの仏像や仏画を紹介しつつ、それらが「仏教思想と信仰」「社会と政治」「異文化と異宗教」という三つの要素とどのように関わってきたかという視点から、仏教美術のもつ意味を読み解く。
宮治 昭[ミヤジアキラ]
1945年、静岡県沼津市生まれ。1968年、名古屋大学文学部(美学美術史)卒業。1972年、同大学大学院博士課程(印度哲学)中退。名古屋大学文学部助手、名古屋大学大学院教授、龍谷大学龍谷ミュージアム館長を経て、現在、龍谷大学特任教授、名古屋大学名誉教授。文学博士。1969年よりインド、パキスタン、アフガニスタン、中国の仏教美術の調査を続ける。専門はインド・中央アジアの仏教美術史。著書に『仏像学入門―ほとけたちのルーツを探る』(増補版、春秋社)、『インド美術史』(吉川弘文館)、『バーミヤーン―京都大学中央アジア学術調査報告』(全4巻、共著、同朋舎)、『涅槃と弥勒の図像学―インドから中央アジアへ』(吉川弘文館、国華特別賞受賞)、『ガンダーラ 仏の不思議』(講談社選書メチエ)、『世界美術大全集 東洋編13・14 インド(1)(2)』(共編著、小学館)、『バーミヤーン、遥かなり』(NHKブックス)など。
内容説明
ガンダーラ、バーミヤーンからキジル、トルファン、敦煌までの、シルクロードの仏教美術を通して、仏像のもつ意味と役割を「仏教の思想と信仰」「社会と政治」「異文化」という三つの視点から考える。図版123点。
目次
序章 仏像を読み解く―インドから中国へ
第1章 バクトリアとクシャーン朝の文化
第2章 仏像の故郷―ガンダーラ
第3章 ガンダーラ美術と大乗仏教
第4章 バーミヤーンの仏教世界
第5章 ガンダーラから敦煌へ
第6章 中央アジアの涅槃の美術
第7章 中央アジアの仏教美術―弥勒信仰・宇宙的仏陀・シルクロードの守護神
第8章 観想と阿弥陀浄土の美術―観経変の成立をめぐって
著者等紹介
宮治昭[ミヤジアキラ]
1945年、静岡県沼津市生まれ。1968年、名古屋大学文学部(美学美術史)卒業。1972年、同大学大学院博士課程(印度哲学)中退。弘前大学助教授、名古屋大学教授、静岡県立美術館館長、龍谷大学龍谷ミュージアム館長を経て、龍谷大学特任教授、名古屋大学名誉教授。1969年よりインド、パキスタン、アフガニスタン、中国の仏教美術の調査を続ける。専門は仏教美術史。文学博士。国華特別賞、中日文化賞、中村元東方学術賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
イツシノコヲリ
月音
-
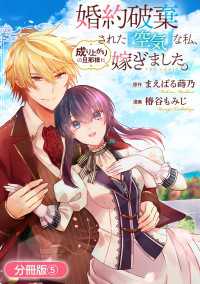
- 電子書籍
- 婚約破棄された『空気』な私、成り上がり…
-
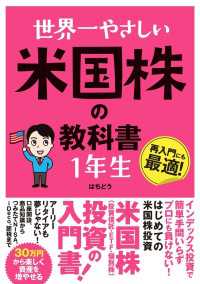
- 電子書籍
- 世界一やさしい 米国株の教科書 1年生