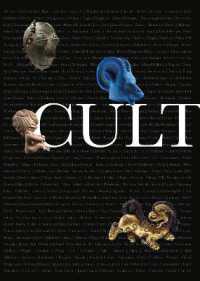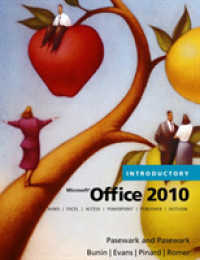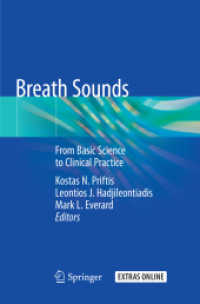出版社内容情報
目からウロコ、今、部落史がおもしろい。
穢多非人という差別用語が日常的に使われていた昔から、現代のいわゆる同和問題にいたる部落差別。それを科学的、歴史的に――つまり客観的に跡付けた著作は意外に少ない。本書はその数少ない客観的な差別解明の書である。
--------------------------------------------------------------------------------
はじめに
亡き丹羽邦男先生にこの書をささげる‥‥‥ ここ二〇~三〇年の間に、差別を撤廃しようとする運動は飛躍的に拡大した。その結果、部落史を研究する人びとの数も急速に増えて、基本となる史料を大量に発掘させたし、歴史を研究する視野や方法を大きく変えさせたのである。そこから、古い説や考え方が崩れ去っていき、現在も、さまざまな説が新しく生まれる最大の要因となっている。
ただ、古いものが壊れようとするとき、えてして新しい考え方はまとまらず、入り乱れがちである。そこから今、同和行政に携わる方がたや学校の先生がたは、部落史をどう理解すべきか、また教えるべきかについて、混乱のただ中で困っておられるように見受けられる。その結果、一度はこの問題にかかわろうと意欲を持った方がたも、気持ちを後退させかねないことを私は恐れている。複雑で面倒な問題には、だれもかかわりたくないからである。
そこで本書は、そうした悩みや混乱に、私なりの「回答」を提出し、部落の歴史に明確な道筋をたて、わかりやすく新たなイメージを生み出そうとしたものである。そして、かつての部落民衆が等身大で本書によみがえり、その表情や息づかいが浮かび上がるよう、できる限りの努力と工夫をした。本書を『よみがえる部落史』と題したのはそのためである。また、この問題を、日本史の領域にだけ閉じ込めず、世界史的な視野から描く姿勢も失わなかったつもりである。 ‥‥‥
二〇〇〇年六月十二日 上杉 聰
よみがえる部落史 ● 目次
序 部落差別はどこから?
部落の歴史を川にたとえると
世界のなかの部落差別
インドから伝わった差別
インド仏教の用語「非人」
仏教と解放思想
第一章 戦国時代に何が起こったのか
差別の制度化が始まる
下剋上で解消されなかった差別
下人をつれた部落民
部落を差別する慣習法
慣習法から成文法へ
法制化による大名の利益
第二章 キリシタンと一向一揆
キリシタンが出会った部落民
「非人」の半数近くがキリシタン
部落の一向一揆への参加
分裂政策への協力
第三章 あいつぐ差別制度化の波
「公儀のキヨメ」
都市空間に写し取られた差別
百姓世界での部落の変貌
写し取られ凝固させられた部落差別
第四章 宗教弾圧が身分を固定
秀吉とバテレン追放令
キリシタン弾圧と部落
宗門人別帳による身分登録
第五章 差別することが義務となる
江戸幕府の部落政策
宗門人別帳が浮き上がらせる身分と夫役
差別することが義務になった社会
「七分の一の命事件」
第六章 民衆にとっての部落差別
部落民としての「非人」
「部落」の内部と地方での多様さ
民衆と部落差別のかかわり
差別に加わる「下」の意識
部落芸能の姿と意味
第七章 差別制度の崩壊に向かって
差別制度が崩壊するメカニズム
穢れ観の後退
幕府の逡巡
差別制度を乗り超える人びと
差別政策を挫折させた民衆
第八章 明治維新の課題となった部落問題
幕末に発生した解放論
維新の内乱に登場する部落民
天皇制による反動と公議所での議論
明治政府内での議論の煮詰まり
第九章 賤民廃止令と反対一揆
開明的で専制的な維新政府
部落の無税地が問題に
賤民制廃止の論理
「布告」理解が生んだ対立
一揆の惨状の中から
部落史こぼれ話
1.見ても穢れる?
2.マヌ法典と日本の部落
3.五〇〇年前のヘリコプター
4.インドは遠くなかった?
5.キリシタンの罪
6.島原の乱と部落
7.フーテンの寅さんと雪駄
8.北海道がない!?
9.大江卓の食器
10.「癩者」と「穢多」
11.聖書にでてくる「穢多」のはなし
12.靴直しをした宣教師
13.弾左衛門の入信
14.聖餐式での差別
15.福沢諭吉と「非人」の娘
16.『学問のすゝめ』と部落
あとがき
内容説明
部落差別はどこから来たのか?信長・秀吉・家康と部落差別の関係は?なぜ解放令が出されねばならなかったのか?などに最新の研究が答える。日本史を変えた新しい部落史。
目次
序 部落差別はどこから?
第1章 戦国時代に何が起こったのか
第2章 キリシタンと一向一揆
第3章 あいつぐ差別制度化の波
第4章 宗教弾圧が身分を固定
第5章 差別することが義務となる
第6章 民衆にとっての部落差別
第7章 差別制度の崩壊に向かって
第8章 明治維新の課題となった部落問題
第9章 賤民廃止令と反対一揆
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
イノ
ソウ
Miki Inoue
Hiroki Nishizumi
Hiroki Nishizumi
-

- 電子書籍
- 少年舞妓・千代菊がゆく!22 恋ごころ…