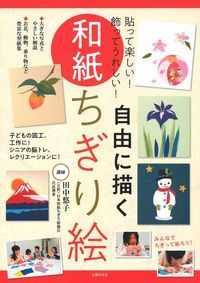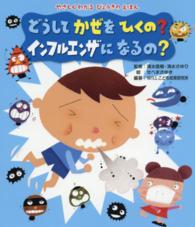- ホーム
- > 和書
- > 社会
- > 社会問題
- > マスコミ・メディア問題
出版社内容情報
なぜ戦争を阻止できなかったか。
戦時下の新聞の生態、新聞の戦争責任を検証する!
過去に学ばないものによりよき未来は開かない。なぜ、国民やジャーナリスト(とりわけ新聞人)の間に戦争への抑止力が生まれなかったのか、という立場から、15年戦争のエポックとなった各事件と新聞報道の内容や姿勢を検証し、巨大な国家暴力が新聞を呑み込んでゆくメカニズムを実証的に描いた労作。
巨大な国家暴力が新聞を呑み込んでいく構造を実証的に描く。
付
● 引用資料・参考文献
● 年表
あとがき
……これまで、本書(および前著『兵は凶器なり』)では一貫して十五年戦争と新聞の関係を検証してきたが、敗戦後に新聞人は自らの戦争責任をどう総括したのだろうか。
敗戦直後から、新聞民主化の波が『朝日』『毎日』『読売』の全国紙はもちろん、地方紙にも拡がり、経営陣や編集幹部が辞職したことは『兵は凶器なり』の「自らを罪するの弁」で詳述した。
しかし、その動きも決して十分なものではなかった。逆に、新聞は自らの戦争責任を自覚し、追及し、反省する姿勢を持続してこなかったといってよい。
政府はもちろん日本人全体が中国、朝鮮、東南アジアヘの侵略や戦争責任に鈍感な体質の中で、新聞ジャーナリズムもその枠を抜け出せなかった。
なぜそうなったのだろうか。その理由の一つは新聞も言論統制の被害者であり戦争責任そのものがないとする考え方である。……
……“新聞被害者論”は当時戦争責任追及と相対立する形で意外と根強く存在し、結局こちらの方が主流となり、戦争責任論は霧散したのではなかろうか。
しかし、これまでみてきたところでは、新聞が戦争をあおった事実は数多くあり、私はこの考え方は被害者意識を強調するあまり一般市民に対する新聞ジャーナリズムの加害性を忘却し、責任を転嫁しており、なぜ言論統制に屈したのか自らの弱点には目をつぶっていると思う。こうした態度では歴史の教訓はくみとれない。
戦争も一度に起こるものではない。問題は戦争が始まってからではなく、戦争にいたるまでの一歩一歩の過程でジャーナリズムがどれだけ歯止めをかけ、抑止力を発揮したかである。
次々に起こる現象にただ流され現実の追認に追われるのではなく、現象の奥にひそむものを的確に見抜く見識、冷静な批判力が必要だが、そのためには戦前の新聞の敗北の歴史の中に学ぶべき点が数多くあると思う。……
内容説明
真珠湾攻撃から50年、戦争は始まってからでは遅い。新聞の戦争責任を検証。戦時下言論史の貴重な資料。
目次
水野広徳の反戦平和思想
軍民離間声明と新聞
永田鉄山暗殺事件
二・二六事件でトドメを刺された新聞
二・二六事件と『時事新報』の抵抗
斎藤隆夫の粛軍演説
スクープ・取引所改革問題
国策通信会社「同盟通信社」の誕生
日中戦争
新聞統制を早めた“紙不足”
南京大虐殺を「武士道の精華」と報道
国家総動員法の落し穴
日・独・伊三国同盟への道
国防保安法による言論封圧
開戦スクープ
太平洋戦争下の報道
歴史をふりかえることは