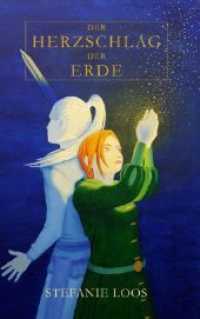出版社内容情報
世紀末へのキートレンドから危機の実態を解明。
日本の経済動向分析が随所に登場するリストラクチャリング・プロセス。
訳者あとがき
本書の何よりも注目すべき大きな特徴は、他におよそ類書が思いあたらないほど資本主義世界経済の実態を全面的、包括的、多面的にあつかい、そしてすぐれて実証的でありながら、しかもこれを体系化して分析しているということであろう。その意味では、同じ著者が前著『世界資本主義の危機』(一九七五年、岩波新書、上下巻)で見せた目標と手腕は、本書ではいっそう全般的に発揮されているというべきである。
著者と同じように広い意味でのマルクス主義の方法論に立つ人びとの研究の圧倒的大部分が、近代経済学の研究にくらべても近来いよいよ個別研究に傾斜し、テーマもいっそう小さく、細分化していく傾向にあるのにたいして、本書にみられるような本来の政治経済学的な実証研究は、最近ではそれだけでも特筆するに値する。
著者のアプローチはまことに正統的(オーソドクス)であって、第1部資本、第2部国家、第3部労働という構成そのものが著者のねらいを明瞭に示している。そして本書が前著以降の、すなわち一九七〇年代後半から現在にいたるまで十余年間の資本主義世界経済をあつかうにあたって、中心にすえている主題は、この時期に顕著となった世界経済のリストラクチャリングのプロセスである。……
著者は、その再構成の過程で言葉の全面的な意味において世界経済と世界市場が成立して、かつ深まったことを論証している。……
著者は、くり返し世界資本主義の経済危機について言及しているが、著者のいう経済危機は、マルクス主義でいわれる循環性の恐慌という意味では必ずしもない。……著者の主張する経済危機とは、何よりも、一九七四年以来しだいに明らかになってきた、投資が生産に向かわずに投機や、M&Aなどに向かう不健全な趨勢、資本主義自体の内包する矛盾の増大を意味している。個別資本の目的はいうまでもなく蓄積、自己増殖、より端的には利潤追求にあることに変わりはないが、その目的が概して財やサーヴィスの生産よりも他の手段、すなわち投機、企業買収と合併、事業分割、乗っとり、為替市場などに向かいつつあるところに、著者は一九七〇年代前半までとは異なる体制の危機の根源を見るのである。……
1989年3月1日 陸井三郎
内容説明
ここ20年の、世界経済の構造的激変は、政治経済的力学の盛衰が過渡的たらざるをえないことを示唆する。投機へ向かう経済、「情報本位制」とも呼ぶべき趨勢と87年10月の大暴落。深まる危機の実態を、日本の動向をおりこみながら、類例のない多面性と包括的手法で解読。
目次
第1部 資本(蓄積、競争、階級闘争;サーヴィス部門;銀行業―中枢部門の変化;工業部門―鉄鋼;新テクノロジー諸産業;兵器産業と経済;原材料と農業における新しい展開;第1部の結論)
第2部 国家(経済の再構成と国家の役割;通貨諸関係;世界債務のジレンマ;世界貿易―その再構成;工業化資本主義諸国の再構成;発展途上諸国;IMFと世界銀行;第2部の結論)
第3部 労働(再構成と労働者階級;雇用の再構成;失業;第3部の結論)
結語