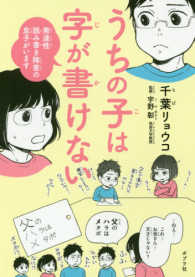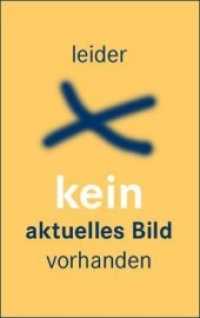出版社内容情報
高橋 富雄[タカハシ トミオ]
著・文・その他
内容説明
「平泉の世紀」それは、地方の一勢力が未開野蛮の地とされていた平泉に、東北全体を支配する政治都市を築きあげ、さらに中尊寺金色堂に象徴される絢爛たる王朝文化の花を咲かせたことを指していう。俘囚長藤原清衡は、日本古代の辺境の歴史において、前を受け、後を定める「かなめ」の位置に立つ人物である。われわれは、彼を通して「平泉の世紀」の歴史を明らかにすることができるだけでなく、東北古代史の総まとめを試みることができるのである。
目次
序 辺境の「かなめ」
1 奥六郡と族長制(俘囚長の系譜;奥六郡の司;前九年の役;鎮守府将軍)
2 藤原の創業(清原清衡;平泉の開府)
3 平泉の世紀(平泉の世紀;相伝のうらみ;平泉文化の論理)
著者等紹介
高橋富雄[タカハシトミオ]
1921(大正10)年、岩手県に生まれる。1943(昭和18)年東北帝国大学文学部国史科卒業。文学博士。東北大学名誉教授。2013年逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ジュンジュン
5
清衡、基衡、秀衡の奥州藤原氏の100年を"平泉の世紀"と位置づけ、その前史と滅亡を加えて描く。一番感じた事は復元の難しさ。辺境ゆえに当時の一次史料である貴族の日記に記述が少なく、敗者ゆえに勝者たる鎌倉側(吾妻鏡他)史料に依拠せざるを得ない。そのため、あらすじは描けても細かい部分(支配体制の中身とか)は難しいのだろう。ただ、大きな流れは分かるし、源氏、平家に続く第三勢力に対する愛情をひしひしと感じる(甘すぎる気もするが)。2019/11/13
Masa03
1
清衡言いつつ、藤原三代(四代)記。 奥州藤原氏といえば、平泉の金色堂と義経というイメージだが、なぜ藤原なのかとか、考えたこともなく、なかなか勉強になった。 特に前九年の役と後三年の役は、なんか東北の反乱と源氏が苦労したよね、くらいの印象しか残ってなかったので、へぇーと思いながら読んだ(もうすっかり忘れてた)。 このシリーズ、こういう出会いがあるからやめられない。2024/05/14
-
- 洋書
- The Dreamer