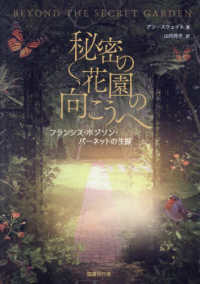目次
第1章 理論編(読むことの教育の構想;「物語を読むって、おもしろい。」と、子どもがつぶやく授業をつくる)
第2章 実践編(おおきなかぶ―おもしろ見つけに挑戦する;あいしているから―価値ある反応を身に付け、主人公の変化を読み味わう;夕日のしずく―気持ち反応を中心に、きりんとありの交流を読み味わう;お手紙―言葉に立ち止まって反応し、登場人物の心の交流や変化を読み味わう;きつねのおきゃくさま―多様な反応をしながら、きつねのやさしさを読み味わう;ピータイルねこ―価値ある反応を生み出しながら、人物同士の関係や主人公の変化を読み味わう;うさぎのさいばん―特長ある仕掛けに根ざした「比べ反応」を中心に、登場人物の知恵や考えの違いを読み味わう;おにたのぼうし―多様な反応をつなぎながら、やさしさの象徴的な表現を読み味わう;白いぼうし―言葉を根拠にした反応で、主人公のやさしさやふしぎな世界を読み味わう;いわたくんちのおばあちゃん―描写表現や人物の関係に根ざした反応を発揮して、親子の愛情を読み味わう;ごんぎつね―表現に即して反応を深化させながら、心のつながりを読み味わう;あたまにつまった石ころが―身に付けたおもしろ反応を使って、グループで伝記を読み味わう;カニモトくん―自分の生活経験に根ざした反応を中心に、物語を読み味わう;競走―「変化反応」「関係反応」を中心に、次第に心のつながりを深めていく人物の関係を読み味わう;大造じいさんとガン―「視点」を拠り所に「変化反応」を発揮し、大造じいさんの心情の変化を読み味わう;竜―作者との対話反応を発揮しながら創作民話を読み味わう;雪わたり―「作者との対話反応」を使いながら、主人公ときつねとの心の通い合いや宮沢賢治の願いを読み味わう)
著者等紹介
田中智生[タナカノリオ]
岡山・小学校の国語を語る会代表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。