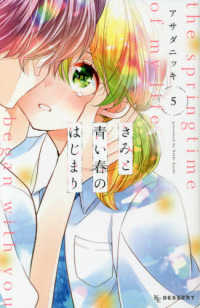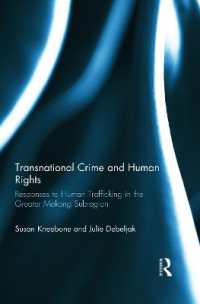出版社内容情報
日本語研究の最前線をゆく執筆陣による「キャラ」と「日本語」をめぐる論文集。縦横無尽に論じる11篇。日本語研究の最前線をゆく執筆陣による「キャラ」と「日本語」をめぐる論文集。「さまざまな「キャラ」」「物語世界のキャラ論」「現実世界のキャラ論」「キャラ論の応用」の4章、縦横無尽に論じる11篇。
定延 利之[サダノブトシユキ]
編集
内容説明
学校ではこんなキャラ、バイト先ではあんなキャラ…「キャラ」についての学際的研究4章11篇!
目次
第1章 さまざまな「キャラ」(キャラ論の前提;日本語コーパスにおける「キャラ(クター)」)
第2章 物語世界のキャラ論(キャラクターとフィクション 宮崎駿監督のアニメ作品、村上春樹の小説をケーススタディとして;「属性表現」再考 「複合性」「非現実性」「知識の共有」から考える ほか)
第3章 現実世界のキャラ論(日本語社会における「キャラ」;ブルデューの「ハビトゥス」と定延の「キャラ」との出会い ほか)
第4章 キャラ論の応用(方言における自称詞・自称詞系文末詞の用法―キャラ助詞とのかかわり;日本語教育とキャラ)
著者等紹介
定延利之[サダノブトシユキ]
京都大学大学院文学研究科教授。博士(文学)。専攻は言語学・コミュニケーション論。軽視・無視されがちな「周辺的」な現象の考察を通じて言語研究・コミュニケーション研究の前提に再検討を加えている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
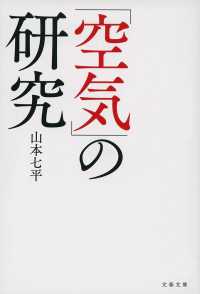
- 和書
- 「空気」の研究 文春文庫