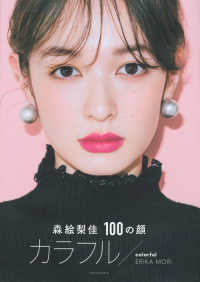内容説明
所有権はいかにして生まれたのか?著者が四半世紀にわたって、農耕社会、遊牧社会、狩猟採集社会、はては工業所有権を生んだ近代社会を彷徨しながら、所有権概念のあり方を、文化人類学的に、法律学的に、また経済学的に検証し、「所有権がなぜ社会に発生したのか」について実証的に解明。
目次
第1章 所有権概念の源を求めて―「所有権」誕生前の世界へ
第2章 土地所有権発生の社会構造
第3章 入会権発生の社会構造―所有、非所有の中間形態としての入会権
第4章 無体財産発生の社会構造
第5章 「権利」の誕生
エピローグ―社会科学・人文科学の統合のなかから
著者等紹介
加藤雅信[カトウマサノブ]
1946年9月9日生。1969年東京大学法学部卒。1973年名古屋大学法学部助教授。1982年名古屋大学法学部教授、現在に至る。1986年東京大学法学博士。この間ハーバード大学客員研究員。ロンドン大学客員研究員。ハワイ大学客員教授。コロンビア大学客員教授。北京大学客員教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Hisashi Tokunaga
0
10年前の読了。ヨーロッパ文明膨張期に侵入された側の民族が土地所有の観念を欠いていたことに留意が必要、と指摘されるんですが、その通り所有の観念はないもののそれ以上の大きな観念体系に包摂されていたですな。民法学者は所有権や契約の概念に迫った論文かかないと気が済まないのかね。(私見)所有権は所有者の眼差しで見える事(現認確認)できる事が必要だ。眼球は水平移動のたやすさの比して、上下移動は困難である。つまり、高地土地は生産性の低さに加えて、確認の難しさが加わることで所有権の差異が?(入会権、共有による)
nobuharuobinata
0
文化人類学の知見から「所有権」の発祥を探究したもの。投下資本の保護と財の稀少性がもたらす価値の保護が私有財産権成立の理由であるとしている。土地所有権を中心に考察されているが同じことは同じく生産財的性質をもつ無体財産権にもいえるという。2022/09/10
-
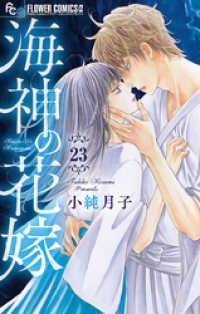
- 電子書籍
- 海神の花嫁【マイクロ】(23) フラワ…
-
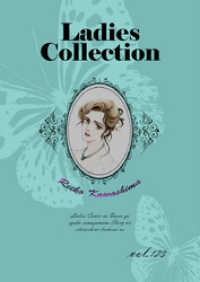
- 電子書籍
- Ladies Collection v…
-
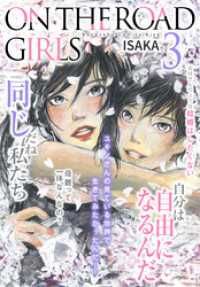
- 電子書籍
- ON THE ROAD GIRLS(3)
-

- 電子書籍
- 「日本の昔ばなし」 ほら吹き娘【フルカ…