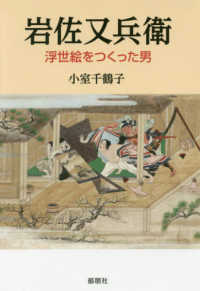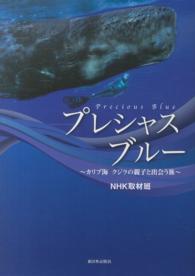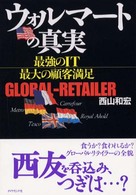内容説明
ウナギはなぜ減少しているのか?どうすれば守ることができるのか?太平洋の産卵場調査はめざましく進んだが、すぐ足もとの川にすんでいるウナギの生活は、意外にもまだ知られていないことが多い…岡山県の児島湾・旭川で調査を行った若き研究者の記録。
目次
第1章 ウナギを研究する(なぜウナギ研究なのか;ウナギの調査を始める)
第2章 ウナギ研究のいま(ウナギの産卵場調査;ウナギ資源を守る ほか)
第3章 研究の現場から(捕ったウナギは大切に;子どものウナギが育つ場所 ほか)
第4章 これからのウナギ研究―ウナギを守るために(ウナギを守るために;ウナギ漁 ほか)
著者等紹介
海部健三[カイフケンゾウ]
1973年、東京都生まれ。1997年に一橋大学社会学部を卒業後、社会人生活を経て2011年に東京大学農学生命科学研究科の博士課程を修了。同年、東京大学農学生命科学研究科特任助教(現職)。2012年より東アジア鰻資源協議会(EASEC)の事務局を担当。専門は保全生態学および水中生物音響学。河川や沿岸におけるニホンウナギの生態のほか、頭足類(イカやタコの仲間)の聴覚を研究している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
じゃすみん
3
中学図書室から。 NHKドキュメンタリ「ウナギ未来への旅」塚本教授の弟子筋な著者。教授は遠くマリアナ海溝でウナギの卵を発見されてたけど、育った幼ウナギが日本の湾や河川でどう育つのかという、著者の研究もとても大事。興味深く読みました。 漁の苦労!耳石! しかし子供向けにしては導入が硬く『柳の葉のようなレプトセファルス』の絵も写真もない!(今時の子供が柳の葉を知るのかw)と思っていたら2章には比較写真もあり、古来『ウナギは卵を産まない』と思われていた逸話など楽しく、ここから始めればよかったのに。2015/09/14
17時のチャイム
3
とてもウナギの生態がわかりやすい本。シラスウナギの捕獲制限以前に、ウナギが遡上しやすい河川を整備しなおすのが先決。2014/09/23
みこよこ
1
ウナギの本と言えば以前「アフリカにょろり旅」という本を読んだことがあります。その時にはウナギの産卵場所を探して、結局見つからなかったのですが、この本ではウナギの卵が2009年に発見されていました。1965年にウナギの産卵場所を探し始めて約50年も探し続けたってすごい!2013/09/27
むにむに
1
ウナギはやっぱり魅力的。筆者が一橋の社会学部卒なのはおもしろい。自分も文系出身だが研究してみたい。2019/03/03
YM
0
わたしのウナギ研究2013/05/23
-
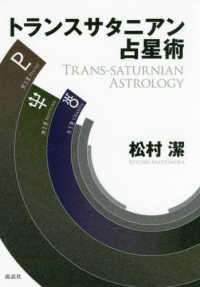
- 和書
- トランスサタニアン占星術