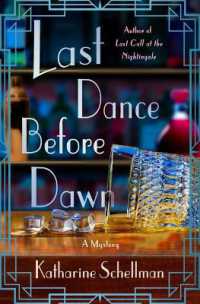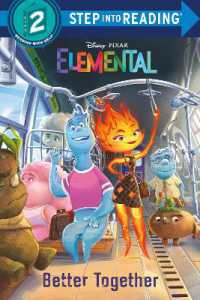内容説明
地球上に生命が誕生してから約20億年間、生物は死ななかった。ひたすら分裂し、増殖していたからだ。ではなぜ、いつから進化した生物は死ぬようになったのか?ヒトは誕生時から「死の遺伝子」を内包しているため、死から逃れることはできない。「死の遺伝子」とはいったい何なのか?死の遺伝子の解明は、ガンやアルツハイマー病、AIDSなどの治療薬開発につながるのか?細胞の死と医薬品開発の最新科学をわかりやすく解説しながら、新しい死生観を問いかける画期的な書。
目次
まえがき 私がなぜ「死」の謎を追うのか
第1章 ある病理学者の発見
第2章 「死」から見る生物学
第3章 「死の科学」との出合い
第4章 アポトーシス研究を活かして、難病に挑む
第5章 ゲノム創薬最前線
第6章 「死の科学」が教えてくれること
著者等紹介
田沼靖一[タヌマセイイチ]
1952年山梨県生まれ。東京大学大学院薬学系研究科博士課程修了。米国国立衛生研究所(NIH)研究員等を経て、東京理科大学薬学部教授。専門は生化学・分子生物学。同大ゲノム創薬研究センター長。細胞の生と死を決定する分子メカニズムをアポトーシスの視点から研究している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ねこ
67
気になった所を3つ①細胞は二つの死がある。「ネクローシス」打撲や火傷など細胞の事故死。細胞膜が破れて中身が飛び出す「汚い」イメージ。「アポトーシス」体からの指令で死にいく細胞。細胞が自ら収縮し、核の中のDNAを切断し、小さな袋に詰め替え断片化し痛みもない。②ガン、AIDS(エイズ)糖尿病、アルツハイマーなど病気と治療薬との解説。③人間の寿命を200年、500年に伸ばしたいので有ればそれに相応しい脳が必要。ただ種の在続という観点からも問題あり。そもそも「死」は「生」に内包されている事か筆者の持論。私も同意。2022/03/05
mackane
19
ヒトはどうして死ぬのか。昔から心の片隅に放置されていた疑問に、ここらでひとつの回答が欲しくて読んだ。本書では、遺伝子がもつ自己死を引き起こすプログラムを通して、その答えに迫っている。なぜ死ぬのかというより、結果として、そういう仕組みの生物が生き残ったというほうが正しいだろう。環境からの刺激やその変化に対応するため、生物は「性」を生み出した。しかし、その結果、死んだほうが良くなったという流れは、好きだ。最後の最後で死を通して考える生きる意味みたいな話に流れちゃったのは個人的に残念。意味がないから奥深いのに。2014/01/21
皆様の「暮らし」を応援サポート
17
この書き方には好感が持てるな。結論はなんかアレだけど。2021/08/05
魚京童!
16
動物は、細胞は、食べて、殖えて、死ぬ。その流れの中で、私がある。私の細胞は昨日の私と同じではない。同じではないが、同じである。その線引きをどこでするのか。私は昨日から連綿と繋がってきた私である必要があるのか。考えたところで答えは出ない。答えはでないけど、愉しい。終わりのない思想。孫子は素晴らしい本というのは納得する。そんなことを考えてないで、戦えと鼓舞してくれる。2024/07/21
たー
15
細胞の死や個体の死は優れた遺伝子を残すために組み込まれたメカニズムであるというのはなかなか説得力のある解釈。が、その死を有るべきものとして寛容する姿勢と、細胞の死のメカニズムを応用して新薬開発を探求する姿勢とが、筆者の中でどう折り合いがつけられているのか疑問に感じた。2011/03/08
-
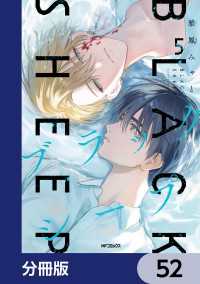
- 電子書籍
- ブラックシープ【分冊版】 52 MFコ…