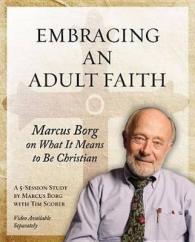内容説明
メール依存、自傷、解離、ひきこもり…「非社会化=未成熟」で特徴づけられる現代の若者問題。しかし、これらを社会のせい、個人のせいと白黒つけることには何の意味もない。彼らが直面する危機は、個人の未熟さを許容する近代成熟社会と、そこで大人になることを強いられる個人との「関係」がもたらす病理だからだ。「社会参加」を前に立ちすくみ、確信的に絶望する若者たちに、大人はどんな成熟のモデルを示すべきなのか?豊富な臨床経験と深い洞察から問う、若者問題への処方箋。
目次
序章 若者は本当に病んでいるのか
第1章 思春期という危機
第2章 欲望を純化するネット社会
第3章 境界線上の若者たち
第4章 身体をめぐる葛藤
第5章 学校へ行かない子どもたち
第6章 ひきこもる青年たち
第7章 「思春期」の精神分析
著者等紹介
斎藤環[サイトウタマキ]
1961年岩手県生まれ。筑波大学医学部研究科博士課程修了。医学博士。専門は思春期・青年期の精神病理学、病跡学、「ひきこもり」の治療・支援ならびに啓蒙活動。爽風会佐々木病院の診療部長として臨床に携わりながら、精神分析、文学、サブカルチャー、現代美術など、幅広いジャンルで評論活動を展開(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヨクト
14
いじめ、オタク、ひきこもり、ニート、リストカット、自殺、殺人者予備軍、情緒不安定…等々。子供と大人の間の理解のしにくい不安定な時期にある若者を異生物のように扱い「今時の若者は…」と括ってしまうのは如何だろうか。実は今に始まったことでないものも多い。未熟さを許容できない社会にも問題があるはず。近年変わったことといえば、携帯やネットといったツールである。ひきこもり系と自分探し系の対比は面白かった。2012/12/27
おっとー
13
若者と精神疾患の関連についての考察。「今頃の若者は~」といった旧来的な観念のもとで若者に責任を押しつけるのではなく、かといって社会や環境が全て悪いと言い切るのでもなく、「病因論的ドライブ」という造語を使って、個々人とその環境の組み合わせが合わないことにより病理が生じると論じていく。若者や社会を一括りにせず、個々の組み合わせを考えていくのはある種スピノザ的な哲学に近い。個別事情を考え、環境との組み合わせを把握し、徐々にずらしていくことこそ、その人にとって生きやすい状況を作ることにつながる。2021/01/17
たりらりらん
7
本書のいうポストモダンは「主体概念」が無効になった時代のこと。「病んで」いるのは個々の要素ではなく、個人―家族―社会という要素間の関係性である。人間関係が膠着し、悪循環になることによって、人間関係が病み、ひきこもりなどの問題につながるのである。本書では、ひきこもりにとらわれず境界例・解離・摂食障害と「若者」について論じられている。本書でも述べられているが、家族療法にヒントを得たとのことで、identified patientの考え方などもちりばめられているように感じた。読みやすく、興味深い一冊でした。 2011/06/12
ころこ
4
斎藤さんは、【個人、家族、社会のそれぞれに、はっきりと指摘できるような病理がなかったとしても、それぞれの「関係」が病理性をはらんでしまうことがある、ということがあるからだ。】といい、この関係要因を、病因論的ドライブと名付けています。 つまり、個人が持っている性質に対し、何とか障害と名付けて、はっきりと治療の対象とするのではなく、個人、家族、社会の関係性を本人にとって適正に補正していくことで、躓きの経験を克服するという考え方をとっています。2016/12/04
ちくわ
3
「病因論的ドライブ」という概念を用いて若者の問題に切り込んでいく。若者の「ひきこもり」等の問題の原因は、「個人」や「環境」といったものに還元されがちである。特に、「心理学化した社会」ともいうべき時代においては、どうしても個人の内面に着目しがちである。しかし、著者は、問題の本質は、個人と環境との間の「関係性」にこそあると指摘する。現代社会は極めて複雑化している。小さな「関係性」が積み重なって日々生きている。このような現代社会を前提にすると、著者の指摘には一理ある。もう少し考えたい。2016/03/24
-
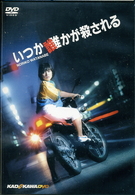
- DVD
- いつか誰かが殺される