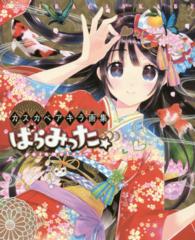内容説明
東日本大震災発災直後、岩手県庁内に設置された災害対策本部で、医療班の指揮にあたったのはある若き医師だった。通信網の崩壊。ヘリが足りない。燃料も不足。支援物資も届かない。雪が、余震が、無情に襲いかかる。「それでも、被災者を救いたい」。張りつめた緊張と混乱の中で、寝食を忘れ奮闘する九日間を綴る、感動のノンフィクションノベル。
著者等紹介
河原れん[カワハラレン]
1980年東京都生まれ。上智大学法学部卒業。2007年、初の長編小説『瞬』を発表。作家活動と並行し、チャリティプロジェクトを主宰。その他、コミック原作、映画脚本、翻訳も手がけている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
百太
22
震災での本人の手記(医療関係者)は、どうしても冷静に淡々と描こうとしてるものが多い中、これは読み物としても読者に伝わりやすく緊迫感がありました。2020/03/21
yamakujira
5
東日本大震災発生から9日間、岩手県災害対策本部の苦闘を、医療班を率いた救命医の視点でえがく。内容はルポなのに小説形式だから、読みやすいばかりでなく、現場の混乱と疲弊が活写されている。この手の本をルポにすると、学術書はさておき、数字の羅列か、涙と感動の押し売りになりがちだから、小説という手法を評価したい。ただ、縦割り行政の弊害を嘆くばかりでなく、秋冨氏の使命感は過剰に思える。マンパワーに依存する災害対策はスタッフの能力に左右されすぎ、もっとシステム化する必要があるだろう。 (★★★☆☆)2016/04/22
ちいちゃん
4
東日本大震災発生直後から、命を救うために全力で奔走した医師の話。単純に、こんなに尽力してくれた人がいたんだと知ることが出来て良かった。内容は重いはずなのに、その重さをあまり感じることなく読んだ。小説としてサラッと読むにはいいけれど、被災者のことを考えると言葉が軽かったり、少し違和感を感じる部分もあった。例えば「瓦礫」という言葉をあまりに軽々しく用いていたが、この言い方を良く思わない被災者も随分多いと聞いた。「瓦礫」と呼ばれるその一つ一つに、生きた証や思い出があるからだそうだ。ともあれ、秋冨医師ありがとう。2019/04/30
まる@珈琲読書
4
★★★★★ 3.11直後の岩手県庁災害対策本部を描いたドキュメンタリー。救援する側の苦悩、行政の機能、支援のされ方・・・考えさせられることが多々ある。もし万が一、同規模、あるいはそれ以上の災害が起きた時どのように対処できるのか。3.11の反省、ノウハウはどこかに蓄積されているのだろうか。一部お役人の当事者意識の低さは事実とすればかなりの問題。非常時に自分の担当ではないという言葉は理解できない。自分の担当ではなくとも組織の使命ではあるはず。非常時に動かなければならないからこそ役人は身分保証されているのでは?2015/06/29
みっちぃ
4
あの日からもうすぐ3年。今この本と出会ったのは、なんの運命か。 岩手県庁の災害対策本部につめる、医療班の医師の一人称で、当時の状況を記したノンフィクションノベル。 当時、まさに沿岸で避難所運営の一端を担っていた時のことを思い出した。現場も情報がない中にあって目の前のことに対処するだけで精一杯だった。いろいろ思い出した。この小説は、多くの人に読んでもらいたい。2014/03/09