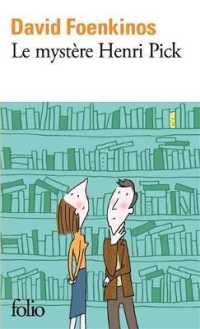内容説明
悲劇はすぐそこで起きていた。放送をきっかけに約7年ぶりに夫婦が再会。国・自治体が対策に着手。社会を動かした「NHKスペシャル」待望の書籍化。
目次
第1章 追跡「認知症行方不明者」
第2章 浮かび上がった深刻な実態
第3章 苦しむ家族
第4章 問われる社会
第5章 浮かび上がった“身元不明者”
第6章 動き出した社会
第7章 私たちにできること
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
85
この本が書かれたのが2014年だから10年経った今は、多分状況は悪くなっていると思う。大阪から札幌にまで移動していた話は驚いた。認知症は全てのことができないわけではなく、突然に昔のことを思い出したり、信じられないくらい遠くにいたりするという。しかし山や住民にいない家の庭でなくなったり、川に落ちたり。そのまま行き倒れで亡くなると身元不明で以前読んだ行旅死亡人として扱われるケースもあるという。認知症の方の介護は悲惨だと思う、それ以上に認認介護、超高齢化、どうなる日本・・・・・・・2024/12/01
nyaoko
66
認知症の行方不明者を搜索、保護する事例として挙げていた韓国の対応はとても効果的だと思った。ただ、今の日本では難しいだろう。一昔前だったら近隣の住民同志の顔が分かっていた。「あの人誰?」と聞けば誰それの家族だと返ってきたものだ。しかし、今では近所付き合いも希薄になり、家族も孤立化し、お年寄りが歩いていても誰も気にしない。自分には要介護者がいると周りに発信する事はとても重要だ。家族が出来ることのポイント解説はとても参考にるので、覚えておかないといけない。いつか来るかもしれないその日のために。2016/03/26
壱萬参仟縁
41
認知症の症状が進むと、言葉を交わすことはできない(3頁)。やだなぁ。軽度認知障害は4百万人に及ぶ(22頁)。認知症の行方不明を把握する公的機関がない(34頁~)。認知症:脳の細胞が死んでしまったり働きが悪くなったりして、物忘れが起こり、生活に支障(54頁)。認知症専用ロボットの開発が追い付かない。テクノロジーが社会問題の深刻化に追い付かないのが現状とわかった。警察だけに頼ることはできないし、期待しても仕方ない。私は警察に不信感を抱く者の一人だからだ。2015/09/17
シュラフ
32
認知症の老人が徘徊することで行方不明となってしまうという現実。いまの世の中で、こんなことありえるのかという驚き。すべては行政と警察の無策による人災のように思える。コンピューターによるネットワークがこれだけ発達した時代なのだから、共通のデータベースをつくれば解決できる問題であろう。ずいぶんいい加減な話である。またもうひとつの問題が個人情報保護法という壁。この法律が行政と警察を臆病にしている。法律なぞ解釈次第でいかにもなるのに、なんたる怠惰であろうか。一家の一員を急に失った家族の辛さはいくばくの思いだろうか。2017/12/24
はなはな
29
認知症の父が行方不明になってから4カ月が経ちます。夏の暑い日だったし、恐らく無事ではないだろうとは覚悟しているものの ほんの少しの希望を諦めるわけにもいかず。同じような思いを抱える人がどのように折り合いをつけているのか知りたくて読んでみましたが、やっぱり折り合いなんかつけられないものなんですね。無事を祈る気持ちと、早く見つけてあげて ありがとう言ってちゃんと送ってあげたい気持ちとがごちゃまぜになってます。2015/11/04