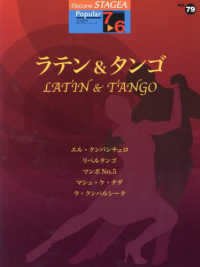内容説明
新種ゾクゾク発見。研究者が生きてる深海生物を激写。世界初公開のとっておき写真満載。
目次
新(暗いのに、派手なメイクをしています―ベニハゼの一種;深海で発見された美しい絞り染め―ベニシボリの一種 ほか)
幻(小さな小さなクリスマスツリーは、単細胞生物と共生細菌だった!―ツリガネムシの一種;暗闇のなか、鮮やかな蛍光は何のため?―イソギンチャクの仲間 ほか)
命(たくましい女性にかじりつく人生―オニアンコウの一種;大きなお母さん、沈木に穴掘る―メオトキクイガイの一種 ほか)
驚(フテてるワケじゃありません―ミドリフサアンコウ;熱水域から、ただ今、見参!―ユノハナガニ ほか)
著者等紹介
藤原義弘[フジワラヨシヒロ]
1969年岡山県生まれ。筑波大学第二学群生物学類卒業。筑波大学修士課程環境科学研究科修了。博士(理学)。海洋研究開発機構海洋・極限環境生物圏領域海洋生物多様性研究プログラム化学合成生態系進化研究チームチームリーダー。広島大学客員准教授。1993年より海洋科学技術センター・研究員、米国スクリプス海洋研究所留学等を経て2009年より現職。深海温泉にくらす独特の生物群の進化や多様性、共生について研究を実施(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
86
2010年出版の本。近くて遠い深海。超高圧の中で生きている さまざまな生き物が紹介された本。 魚、貝、エビ、イソギンチャク、ホヤ。まだ他にも。 出版から15年、深海探索も進歩しているので 新種の生き物も多く見つかっていると思う。戦争の武器云々を 作る金と技術を深海探査に転換すると、地球のエネルギー問題の 解決の糸口も見つかるかもしれないし、海中の二酸化炭素を 減らせるアイデアも出てくるかもしれない。 図書館本 2025/10/04
鱒子
29
図書館本。さすが深海生物、「〇〇の仲間」や「〇〇の一種」と表示され、学名がついていないものだらけの本です。半透明の体を持つものが多いですね。研究のため飼育されているボテちゃんジュニアがとても可愛いです。2016/12/08
ツバメマン★こち亀読破中
22
まだまだいる深海生物。ダイオウクソクムシ意外は、よくある深海魚本にはあまり掲載されていないのでは?300℃の熱水が吹き出す深海で生きる巻き貝の仲間、小さなオスが大きなメスと出会うとくっついてメス一部分となってしまうアンコウの仲間等々…“生き物”という概念を今一度考え直さなければならないかも…。2016/03/31
鯖
21
座礁したマッコウクジラ12体を沈め、人為的に作られた鯨骨生物群集で発見されたゲイコツナメクジウオが姿もすごいけど、発見の経緯もなんかすごいなあ…。海底火山の湧き出す熱水チムニーのそばに暮らすユノハナガニは甲殻類なのに、熱で赤くならない。イトエラゴカイは羽根みたいな飾りがきれいなのに、ピンクのパスタの塊みたいなのをゴバっと吐き出して、網にして微細な生き物をからめとって食べる。ビジュアル的にアウトだった。2019/06/05
那由多
19
グソクムシとかゴカイやウロコムシの足ウジャウジャ系から、強面オニアンコウ、樹氷のように華麗な見た目に反して細菌のかたまりツリガネムシまで色々。水槽で飼われているボテちゃんジュニアが、持ち上げられてる姿の妙な可愛らしさ。イトエラゴカイが口から出す触手は、寄生虫にしか見えない。そういえば、触手や又はそんな見た目の器官を持つ生物が、深海には多い気がする。2019/10/16
-

- 和書
- 雷神 新潮文庫