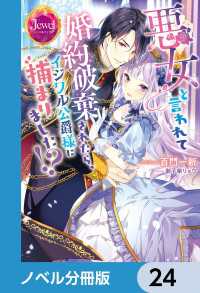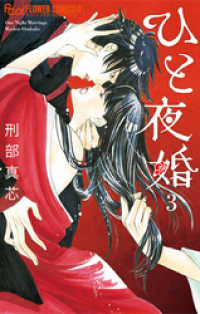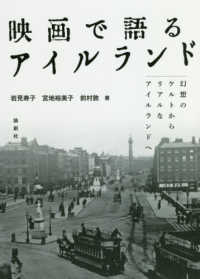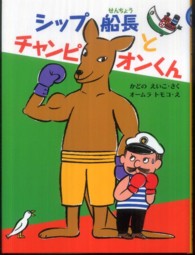内容説明
いなせな職人、婀娜な女房、野暮な男、通なお大尽…。八百八町の風俗まるわかり。現代に残る江戸言葉の成り立ちから長屋暮らしの庶民生活まで楽しく紹介。
目次
第1章 江戸っ子の粋な言語学(「江戸っ子」といえるのは、どんな人物か;「ちゃきちゃきの江戸っ子」―ちゃきちゃきって何? ほか)
第2章 大江戸八百八町の光と影(江戸には町がいくつあったのか;江戸の人口はどれくらいだったのか ほか)
第3章 大江戸の面白稼業あれこれ(質屋の看板は駒形、その理由は?;押し売りも同然、「銭緡」の行商 ほか)
第4章 花のお江戸のびっくり蘊蓄ばなし(江戸っ子は下帯(ふんどし)を捨てて厄払い
江戸っ子の生まれそこない、金を持ち ほか)
第5章 江戸川柳の微苦笑歳時記(初夢と宝船、その関連とは?;薮入り―何日くらい休めたのか ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しゅわ
50
【図書館】第一章で江戸言葉の成り立ちやそこに息づく粋、第二章はお江戸八百八町…特に長屋暮らしの庶民生活に関して紹介、第三章では江戸の職業…後半は吉原関係を詳しく、そして第四章でビックリなウンチク…という構成で、わかりやすく江戸の人々の生活を解説する一冊です。ひとつひとつの豆知識がとても短く、読みやすい構成。川柳などの具体例があるので、楽しく理解できます。できるなら、道具の説明等でイラストがればよかったなぁ。2015/10/24
onasu
19
お江戸の諸般を著した作品は数あるので、物珍しいことはないのだけど、掲載ネタ、文量ともに適当な作品でした。 タイトルは、江戸後期の見世物興行で、江戸ものが大坂に負け、その大坂が長崎に負けたので、長崎「が」江戸の仇を取ってくれた、と言われたとか。タイトルへの苦心は偲ばれるけど…。 「へえ〜」の一番手は、元禄〜享保の一時だけ、南北の他に中町奉行所があった、て話し。次いでは、数編あった下ネタ系。両国米沢町には大人の店があって、店内は暗く、通信販売もしていたとか。この辺、お江戸には大抵のものはあるのだよね。2015/04/07
ペイパル
0
当時、江戸は100万人の人が暮らす世界最大の都市でした。毎日大量に発生するゴミはどう処理されていたのか、モノのリサイクルはどのように行われていたのか、ということに興味があったので、手にとってみました。それによると、まず「ゴミ」という概念がなかったらしく、何から何まで消費した後の引き取り屋・修理屋が存在し、リサイクルの流れがきれいな円を描いていたようです。食べかす・糞尿も作物の肥料になるので、ところかまわず排泄していた西欧と比べても日本人のキレイ好き・もったいない精神は当時から際立っていたんですね。2016/06/04