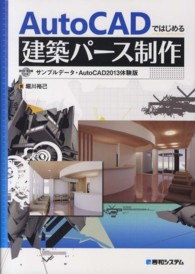内容説明
大階段・羽根飾り・銀橋…見る人を夢の世界へと誘う、宝塚レビューならではの舞台演出。アマチュアリズムの根底となる宝塚音楽学校。新聞メディアとの共存共栄―小林一三の独創性に端を発して、意外な広がりをみせるタカラヅカ文化の数々の歴史を、さまざまな角度から明らかにしていく。
目次
対談 「大阪人・上方文化・宝塚歌劇」
インタビュー(紫苑ゆう―退団後のこと;夏城令―宝塚の思い出)
宝塚歌劇、その演出の妙味を探る
白井鉄造とシャンソン
レビューに見るオリエンタリズム
鴨川清作の思想と作品―第二作『邪宗門』について
庄野英二と高木史朗の『星の牧場』
回想 演出家・小原弘稔の思い出
宝塚音楽学校の創立と変遷
宝塚歌劇における脚本公募史
昭和初期の舞台衣装―木下真からの聞き書きを中心に
阪急学園そして池田文庫・宝塚文芸図書館
“日本ジャズの父”井田一郎と宝塚歌劇
小特集 宝塚歌劇と新聞メディア
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
qoop
0
初期の宝塚に関わった様々な人々に焦点を当てることで、複層的に宝塚歌劇の全体像を掘り起こそうとする試みとして一冊まとまっている。細部から全体を見返していく面白みがある。収録作中、特に徳山孝子〈昭和初期の舞台衣装〉が興味深かった。洋装の受容史としていうのは馴染みがないこともあって感心しつつ読んだ。短文なのが惜しいけれど、衣装部設立当初から在籍していた木下真氏が100歳でご存命でなければ、こうした話も残らなかったかも知れないのかと思うと、100周年を迎えた宝塚の歴史の長さを改めて意識する。2014/06/10
-

- 和書
- 政治算術 岩波文庫