内容説明
吉宗が将軍職を継いだ享保の時代は、現代と同様、危機の時代であった。歴代将軍の放漫財政がたたって、元禄時代以降、幕府経済は窮迫し、旗本に給料を支払えないようなありさまだった。そのような状況にあって、吉宗は“長耳の発想法”とも言うべき独自の情報収集術をもとに、みずから先頭に立ってつぎつぎと改革を行ない、この危機を乗り切る。本書は、享保の改革を支えた吉宗の政治手法とその人となりをわかりやすく述べたものだが、半歩先が読めない時代である現代にも充分に生かされるはずである。
目次
序 吉宗の改革を支えた“長耳の発想法”
1 おのれの声しか聞かぬなら、耳など無用の長物―吉宗の情報収集術(政治もまた戦である―旧幣の官僚組織を震撼させたお庭番と目安箱による情報収集;戦略の神髄は機を待つことにある―つねに情報を集めて、自分にもっとも有利な“時”を見極める ほか)
2 巧ある者を賞して功をなさしめよ―吉宗の人心掌握術(優駿は異なところにいるのが世の常―前例破りの抜擢人事によって改革を推進する;梅園は鴬が鳴いてさらに色づく―身分や前歴にとらわれない適材適所の成果 ほか)
3 乱世には詭道も正道となる―吉宗の経営改革術(山野に水を引き、海浜を耕す―自前の生産物の拡大と管理組織に人材を投入する;禁酒を説くなら、まずは酒器をこわす―百万言よりも実行こそが旧幣を打ち破る最善の法である ほか)
4 幕政の礎は序列にあり―吉宗の組織管理術(法に任じて人に任ぜず―改革を妨げるものは官僚だけではなく、その組織自体を守る法制に原因がある;諸事権現様(家康)のお定めどおり―無用と思われるものでも、組織維持に役立つものはのこす ほか)
著者等紹介
八尋舜右[ヤヒロシュンスケ]
1935年生まれ。早稲田大学文学部卒業。『歴史読本』編集長時代から歴史小説を意欲的に発表する。その後、朝日新聞社図書編集室長を経て、94年より作家活動に専念。日本ペンクラブ・現代詩人会会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 酔い醒めのころに
-

- 電子書籍
- 終末世界のバトルテック 【タテヨミ】第…
-

- 電子書籍
- 異国の誘惑【分冊】 1巻 ハーレクイン…
-

- 電子書籍
- 目覚め - 本編
-
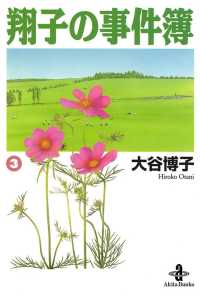
- 電子書籍
- 翔子の事件簿【秋田文庫版】 3 エレガ…



