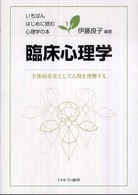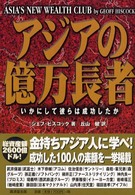目次
導入
第1部 基礎編(変数と計算;制御構文;関数;クラスとオブジェクト指向)
第2部 展開編(ファイル操作;整数を扱う計算;数値計算;ベクトルと行列;最適化問題)
付録
著者等紹介
大和田勇人[オオワダハヤト]
1983年東京理科大学理工学部経営工学科卒業。1988年東京理科大学大学院理工学研究科博士課程修了(経営工学専攻)、工学博士。東京理科大学助手。1999年東京理科大学専任講師。2001年東京理科大学助教授。2005年東京理科大学教授
金盛克俊[カナモリカツトシ]
2004年東京理科大学理工学部情報科学科卒業。2009年東京理科大学大学院理工学研究科博士課程修了(情報科学専攻)、博士(理学)。フリーランスでアプリ開発業務に従事。2012年東京理科大学助教(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
日輪
2
プログラミングは未経験だけど、Python3で数値計算を学びたい人に適した本だと思った。Pythonの超基礎的な構文から、変数やリストに対する演算、関数の利用法、クラスとメソッド、ファイル操作、モジュールのインポート、数値計算や最適化など、必要そうなこと全てを効率的に解説している。方程式の解や微分積分はSymPyでもっと簡潔に書けるし、可視化もmatplotlibを使うのが普通だが、処理をブラックボックス化せずに学ぶには遠回りも重要なこと。クラスを使ったナップサック問題のプログラムも分かりやすかった。2017/02/28
くらーく
1
第7章までかな。8章以降はついていけず。ま、仕事じゃないけど。もう頑張るような年齢でも無いし、そこまで情熱も無い。。。 東京理科大卒の新入社員は、この程度を勉強してきたんだろうなあ、とか思ったり。若い子達のスキルの高さを上手く使えているのかねえ、大企業は。 それと、Pythonのコードの短さには驚くなあ。大体1ページで収まるものねえ。コード1行でいくら、なんて時代もあったのにねえ。 どうでも良いけど、なぜ読書メーターでは「PYTHoN」なんだ?書名は「Python」なのに。2020/06/16
ぶひん
0
数値積分のやり方や、ファイルの読み書きが特に参考になりました。2017/04/08
ゆかりん
0
電子工作の勉強会に先駆けて、サラッとpythonを予習。他のプログラミング言語を習得済みなら、この本は軽く読めるし、演習も適切です。2016/10/10
五十嵐
0
後半、ガチ数学になるところが文系には厳しい。2023/09/25
-
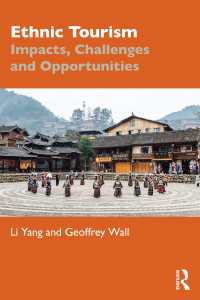
- 洋書電子書籍
- Ethnic Tourism : Im…