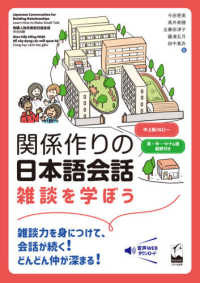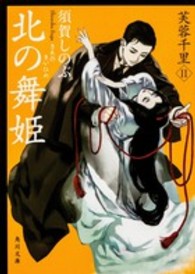内容説明
日本の子どもたちが出会う、さまざまな行事やならわしの、はじまりやわけが、この本でわかるように、やさしくかきました。先祖の人たちがおまつりやしきたりにこめた願いや心が、ただしくつたわるようにくふうしましたので、どうぞたのしんでよんでください。
目次
11月の別のいいかた(日本)
文化の日(11月3日)
灯台記念日(11月1日)/小春日和
酉の市
立冬(11月7日ごろ)/ふいごまつり(11月8日)
刈り上げまつり
亥の子・十日夜/わら
いろいろなおち葉
11月の鳥/11月の魚
いろいろな紙ひこうき〔ほか〕
著者等紹介
かこさとし[カコサトシ]
本名、加古里子。1926(大正15)年福井県武生町(現・越前市)生まれ。1948年東京大学工学部卒業。工学博士。技術士。民間化学会社研究所に勤務しながら、セツルメント活動、児童文化活動に従事。1959年出版活動にかかわり、1973年に勤務先を退社後、作家活動とともに、テレビニュースキャスター、東京大学、横浜国立大学などで児童文化、行動論の講師をつとめた。また、パキスタン、ラオス、ベトナム、オマーン、中国などで識字活動、障害児教育、科学教育の実践指導などを行い、アメリカ、カナダ、台湾の現地補習校、幼稚園、日本人会で幼児教育、児童指導について講演実践を行った(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kaizen@名古屋de朝活読書会
55
11月は霜月。文化の日、灯台記念日、小春日和、酉の市、立冬、ふいごまつり,刈り上げ祭り,亥の子・十日夜,七五三、時雨、えびす講,小雪、冬眠などの行事、言葉の説明。わらなわのつくりかた,モミジやかえでの遊び、落ち葉のダンス、柿の葉人形、イチョウの人形,紙飛行機,わらぞうりのつくりかた,スプーンの絵・音あそび,てのひらぶーめらんなどの説明。あたたかいたべものとして,葛湯、三平汁、かまあげうどん,けんちん汁、おでん、なべやきうどん,のっぺい汁、しょっつるなべの紹介。2013/09/29
遠い日
4
11月の行事と生活。子どもに引きつけてみても、たくさんあることに驚く。今に伝わるものと、今は多分行わないところの方が多いかもしれないものも。それにしても、日本ではこうして季節、時節ごとの小さな節目を大切にしてきたことに今さらながら気づかされる。2016/12/23
-

- 和書
- おっぱい、みつけた