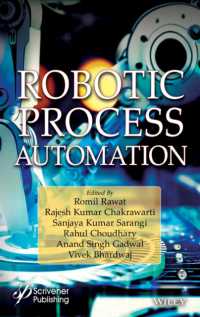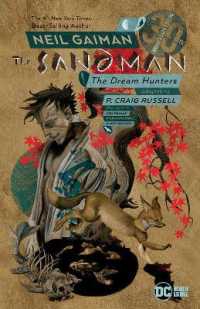内容説明
最初のアフガニスタン取材が始り、このとき「生活の場が戦場になる」ことを知りました。帰国して撮影したフィルムを現像すると、アフガニスタンの人々は、瞳の奥底から生きる力を強く訴えていました。著者は、より多くの人々と話をするため学校の教室や集会場にでかけました。そこで大きく引伸ばした写真を展示し「フォト・ディスカッション」を行って、いろいろな人と話す機会を得ました。そして今、私の手元に日本のこどもたちからの感想文が集まってきています。その一部ですがアフガニスタンの言葉にも訳して写真と共に紹介します。
著者等紹介
内堀たけし[ウチボリタケシ]
写真家。1955年東京生まれ。「なにげない日常」をテーマにルポルタージュを続ける。海外取材は40ヵ国に及び、特にポルトガル・スペイン語圏に精通する。一方、俳句関連の取材で国内各地の暮らし、風土、行事などを撮影する。「俳句・季語入門 全5巻」(国土社)の写真を担当。NGOカレーズの会、(社)日本写真家協会会員。写真の可能性を追求する「写壇ぺん」代表
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヒラP@ehon.gohon
30
20年前の写真絵本ですが、アメリカがアフガニスタンから撤退した現在、決して昔のこととして軽いに持ちになれない本です。 この本に登場した子どもたちは、今どうしているでしょう。 日本と距離感をもって見てしまう自分ですが、写真の中に添えられた子どもたちの言葉も気にかかりました。 20年経って、その時の思いを大切に育っているだろうか。 平和を祈る気持ちは不変で有りたいと改めて実感しました。2023/06/20
shiho♪
17
『ランドセルは海を越えて』の内堀タケシさんの2004年の写真絵本。今年同じタイトルの新版が国土社から出たのでそちらも読んでみたい。 戦争の傷痕残るアフガニスタンの子どもたち。 一日中、休日もなく働く子どもたちの姿。子どもたちは難民キャンプにいる家族の暮らしを支えている。学校に通う子どもたちは、多くの子が小さな妹や弟を抱いて学校へ。赤ちゃんをあやしながら一所懸命に授業を受けている。 子どもたちの眼差しがこんなにも力強いのはなぜなのだろう。家族を大切にし、たくましく生きる子どもたちの姿。小学高学年向け。 2021/05/07
とよぽん
12
写真のほとんどが、アフガニスタンの働く子供たちだ。貧しくても瞳や表情が明るいのは、未来に希望をもっているからだろう。内戦で破壊されたままの建物、学校、打ち捨てられた戦車、不発弾、地雷も人々の生活の場に残っている。内堀たけしさんの他の写真集も見てみたい。2017/02/12
lovemys
8
長男が小学生のときにアフガニスタンから来た子と仲良かったので、アフガニスタンの写真をみると、ついつい手にとって見てしまう。彼らはアフガニスタンに帰国したけど、どうしてるだろう。すんごく人懐っこくって、兄弟姉妹仲が良かったのを覚えてる。いつも戦争ばかりのイメージだけど、みんなよく話し、よく笑って楽しい子たちばかりだったな。この本の子どもたちの笑顔も素敵。アフガニスタンに平和が訪れますように。2021/10/09
れい
8
【図書館】日本の子供たちのコメントが所々に散りばめられているけれど、心にズンと来たのが、『だれかがしあわせだと、だれかがふこうなの?』という言葉。幸せは平等ではない。しかし、人によって幸せ感も変わるのが真理。物が豊かでも人と人との繋がりが希薄で冷淡な世界に住む人と、貧しくてお腹を空かせていても家族との絆や人の暖かさがあるのは、どちらが幸せだと思うのか?2017/05/18
-

- 和書
- 物語日本史 9