出版社内容情報
「ゴジラ」を生んだ本多猪四郎の人生と創作の秘密を、緻密な調査と分析で解明する撮影所年代記。生誕百年記念の待望の復刊!!
【著者紹介】
映画評論家。著作に『黒澤明の映画術』(筑摩書房)、『大島渚のすべて』(キネマ旬報社)、『「砂の器」と「日本沈没」70年代日本の超大作映画』(筑摩書房)『ロマンポルノと実録やくざ映画禁じられた70年代日本映画』(平凡社新書)などがある。
内容説明
『ゴジラ』を生んだ本多猪四郎の人生とその創作の秘密を、緻密な調査と分析で解明するユニークな“撮影所年代記”。生誕100年を記念して待望の復刊。
目次
第1部 撮影所の時代(『ジゴマ』の年に生まれて;森岩雄ともうひとつの「金曜会」;P・C・L入社と青春の蹉跌;P・C・Lから東宝映画へ;山本嘉次郎の「作家」性 ほか)
第2部 監督本多猪四郎(映画芸術協会と『野良犬』のころ;デビュー作と『羅生門』;プロデューサー・システムの再建;円谷英二との出会い;『ゴジラ』前夜の模索 ほか)
著者等紹介
樋口尚文[ヒグチナオフミ]
1962年生まれ。映画批評家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kokada_jnet
24
切通理作『本多猪四郎 無冠の巨匠』の中で、本多監督を「単なる職人監督」と決めつけていると、言及されている本。
ぐうぐう
8
1992年に刊行された本書が、2011年、本多猪四郎生誕100年の年に復刻され、今年2014年、『ゴジラ』誕生60年の節目の年の読書となった。が、これは『ゴジラ』第一作の撮影秘話をまとめた内容のメイキング本ではない。サブタイトルにあるように、本多猪四郎という映画監督を、撮影所から眺めた、とても斬新な本多論となっている。当時の撮影所システムが求めた職人としての監督達。(つづく)2014/07/10
ヒデキ
5
本多猪四郎監督の映画人生を通して戦前からの映画業界の流れと東宝という会社の流れを描いています。本多監督が何故、特撮映画の監督になっていったのかがとっても面白く描かれていますが、それは映画監督としての本多監督にとって良かったのかな?と思って読ませて貰いました2020/01/09
たいそ
3
撮影所のシステムを通して見た本多猪四郎監督の年代記。作家と職人、コンティニュイティとビジュアルといった対比がおもしろかった。森岩雄氏が特撮に要求していたものであったり「監督」の呼称を変えたりといったところも興味深い。また1958年から1964年の映画人口の変化が驚異的で、そのあたりでの作品の質の変化と照らし合わせるとなるほどと思えた。「本多は映画作家でありながら、撮影所では最後の最後まで自分らしさの表現を認められなかった職人の典型。」 2013/10/27
n_kurita
0
ゴジラ、話題だし…しかし本多猪四郎とは言いつつも、第1章は撮影所や同年代の映画作家について書き、外堀を埋めていく。第2章は本題、本多猪四郎についてをより深く。ちょっと文章の書き方が自分と合わなかったのか、ちょっと読みづらい。でも面白かった。切通さんの書籍と一緒に読むとなお良し。2016/08/25
-

- 電子書籍
- 世界の終わりの世界録【分冊版】 113…
-

- 電子書籍
- 雪、ときどき自由(話売り) #6
-
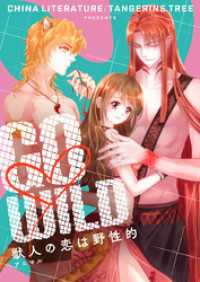
- 電子書籍
- GO WILD~獣人の恋は野性的~【タ…
-
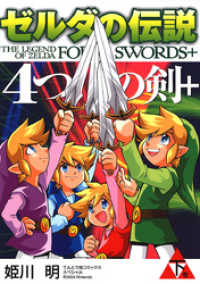
- 電子書籍
- ゼルダの伝説 4つの剣+ 下巻 てんと…
-
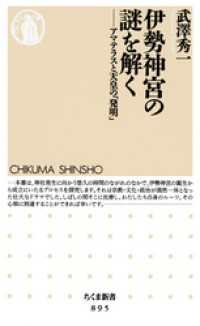
- 電子書籍
- 伊勢神宮の謎を解く ──アマテラスと天…




