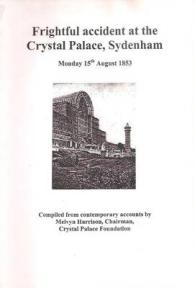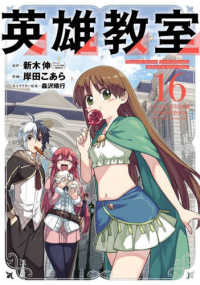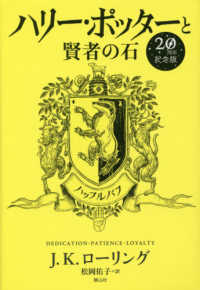内容説明
電子書籍元年、紙の本はいずれ亡びる―そんなバカな!せわしないビジネス談義の前に、電子化への動きを五千年におよぶ長い書物史・文明史の流れのなかでとらえなおしてみよう。二つの本のかたちが共存する新しい時代が見えてくるはずだ。電子本黎明期より本と出版の未来を考察してきた第一人者による明快な読書論。書き下ろし“書物史の第三の革命”と、萩野正昭氏との対談も収録。
目次
1 書物史の第三の革命(本と読書の世界が変わる;「本の黄金時代」としての二十世紀;売れる本がいい本 ほか)
2 電子本をバカにするなかれ(2001もし私が二十一世紀の出版史を書くとしたら;2001無料情報の大海のなかで;2002私はコンピュータ嫌いになりそうだ ほか)
3 歩く書物―ブックマンが見た夢(レイ・ブラッドベリ再読;来たるべきホメロス;『坊っちゃん』の変形 ほか)
著者等紹介
津野海太郎[ツノカイタロウ]
1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、演劇と編集に携わる。劇団「黒テント」制作・演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長を歴任。主な著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(平凡社、新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(平凡社、芸術選奨文部科学大臣賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
樋口佳之
46
読んだのは「書物史の第三の革命」のみ/政治的主張が忌避される中で「革命」って言葉だけは多用されるなあ。ここにも。/最近、スキャン→OCR→テキスト読み(+誤認識修正)っていうデジタル写経みたいな事を試みているのですが、フォントとサイズの選択、行間の自由さ、誤認識修正のためにそれなりに文章に向き合っているなど、前準備があっても、目をしょぼしょぼさせて小さな細い文字を追うよりずっと良い感じ。仕事関係で三四十年モニターに向き合ってきたからかもしれませんが、電子本は高齢者にこそありがたいと思うのだけど。2023/11/28
Susumu Kobayashi
6
書物史において、口承から書記へを「第一の革命」、写本から印刷本へを「第二の革命」とし、印刷本から電子本への「第三の革命」について論じた本。第一部「書物史の第三の革命」は書き下ろしだけあって統一感があるが、第二部以降は既発表の文章を集めたもので、いささかちぐはぐな印象を受けた(第二部の表題が本書の題名になっている)。電子本はスペースを取らないし、検索にも圧倒的に有利だが、物理的実態がないと人間は愛着やら何やら付随する感情を持てない。適度な棲み分けということで手を打つ(?)ことになるんだろうな。2018/01/07
やす
5
さすがに古さは感じるが、電子書籍と紙の本との共存を目指して書かれた、先見の明がある本。 スマホが全く出てこないのは少し古いせいかな 第二部以降はバラバラな感じ2019/01/18
Miyoshi Hirotaka
5
書物は口承から書記へ、写本から印刷本を経て電子化の時代に突入した。これは、電子本が残って印刷本が淘汰されるという単純な図式ではない。物質の本と物質でない本の二系統の共存時代の始まりであり、文字のない世界で口から口へと語り伝えられた口承文化の世界への回帰ともいえる。その中で、社会の知の水準を維持する使命、知に権威を与える機能、広大な無料情報を提供する機能を調和させることが必要だ。2012/05/04
takao
3
ふむ2019/12/05