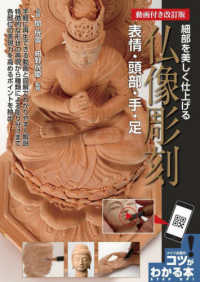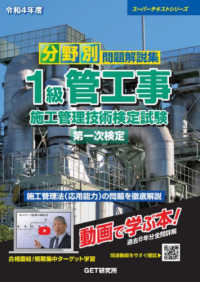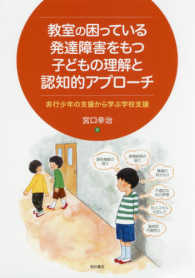内容説明
人間の欲をかき立て、生活をにぎる鍵ともなる「円」がたどった激動の歴史を、雑誌や新聞の諷刺画300点をもとに追う、絵で見る日本経済史。
目次
1 幕末・明治篇(開港と貨幣問題―狙われた日本の小判;金の流出―押し寄せるメキシコドル ほか)
2 大正篇(第一次世界大戦と軍事費―秘密裏に多額の戦費の支出が決まる;物価調節令―横行する買い占めに実効少なく ほか)
3 昭和・戦前篇(昭和金融恐慌のきっかけ―片岡蔵相の発言が取り付け騒ぎを招く;モラトリアム―高橋是清、助っ人に入る ほか)
4 昭和・戦後篇(新円切り替え―続くインフレに効果は薄く;統制経済―極度の物資不足のなか、公務員ばかりが増える ほか)
5 平成篇(消費税導入―社会保障費に、国債の利子に…戦後税制の大改革;日米構造協議―大方の見方は「アメリカの圧力に屈する日本」 ほか)
著者等紹介
湯本豪一[ユモトコウイチ]
1950年東京生まれ。川崎市市民ミュージアム学芸室長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゲオルギオ・ハーン
21
正しいサブタイトルは『幕末から平成まで』当時の経済的な話を風刺画とともに紹介している。経済学的な解説は著者が民俗学者のため、ちょっと説明不足な話で終わっているためその点はあまり面白くなかった。面白かったのは風刺画の変化で政治家個人の知名度が上がっていくと風刺画にも登場するようになる。なので幕末や明治初期は似顔絵やデフォルト化した絵がない。さらに読み進めると線の数を減らし、構図が洗練されていくことでひと目でなにが言いたい絵か分かるようになる。戦中が抜けているがこれは風刺画が禁止だったということだろうか。2023/08/19
メルセ・ひすい
2
14-37 赤39 貴重本 写真 風刺画 挿絵 漫画多数搭載 明治に生まれた統一通貨・円。人間の欲をかき立て、生活をにぎる鍵ともなる円がたどった激動の歴史を、雑誌や新聞の諷刺画300点をもとに追う、絵で見る日本経済史。〈湯本豪一〉1950年東京生まれ。川崎市市民ミュージアム学芸室長。著書に「近代造幣事始め」「図説明治事物起源事典」など。2010/12/21
緑のたぬき
0
幕末から平成版を読む。日本の通貨、円の歴史について、各時代の新聞などの絵図、記事を用いて解説。中東戦争時の物価上昇、米からの軍拡要求、政府債務増加による消費増税、安倍黒田の量的緩和バブル、過去と同じことをしていて今に重なって見える。2023/02/11
-

- 洋書電子書籍
- 心理学と宗教百科事典(第3版・全3巻)…