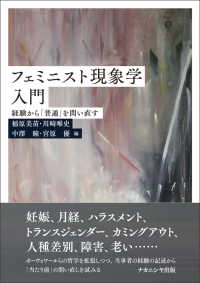内容説明
「こう上下の瞼を合せ、じいッと考えてりゃあ、逢わねえ昔のおッかさんの俤が出てくるんだ」番場の忠太郎は五つの時に生き別れた母親をたずねる旅をつづけていた―不朽の名作「瞼の母」ほか「沓掛時次郎」「一本刀土俵入」「雪の渡り鳥」など傑作戯曲を全七篇収録。
著者等紹介
長谷川伸[ハセガワシン]
1884‐1963。横浜生まれ。小学校を中退し、土木請負業の現場小僧や鳶人足など職を転々とし辛酸をなめる。二十歳のとき横浜新聞社に入社、都新聞に転じ、かたわら創作を開始。菊池寛に認められ「夜もすがら検校」によって文壇の地位を築く。昭和3年に発表した「沓掛時次郎」で、いわゆる“股旅”ものの流行作家となる。「二六日会」「新鷹会」といった勉強会を自宅で開いて、大衆作家の育成に尽力し、ここから村上元三、山手樹一郎、山岡荘八、池波正太郎、平岩弓枝らが育った(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kayak-gohan
22
映画や舞台等で名前だけは知っていた「瞼の母」、「沓掛時次郎」、「一本刀土俵入」等々、そしてその主人公たち。あらためて作品をきちんと読んで内容を知るとともに作者・長谷川伸の人となりに迫ってみようと思い傑作選三冊を購入。本編がその一本目。渡世人や博徒が登場するものばかりだが、そこで描かれるのは義理の重さを受け止めつつ、土壇場で見せる人間としての情。全作とも当時の市井に生きる庶民の暮らしぶりや地域の様子が丁寧に記述されており、背景に綿密な調査と考証があることを窺わせる。引き続き二本目の股旅を共に歩くこととする。2018/09/01
takao
2
ふむ2024/12/21
Shigeo Torii
0
表題作と沓掛--と一本刀--も3作のみ。活字にすると、こんなに短かいとは。芝居で(勿論一級の役者で)見たいものだ。2013/04/16
skydog
0
名作揃い。
ヨウゾウ
0
「瞼の母」「沓掛時次郎」「一本刀土俵入」「雪の渡り鳥」「中山七里」「勘太郎月の唄」「直八子供旅」の股旅物七編。 題名は有名ですが、ストーリーには馴染みがありませんでした。劇場での芝居を見てみたいものです。2025/02/17
-
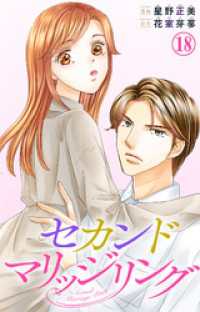
- 電子書籍
- セカンドマリッジリング 18 素敵なロ…
-

- 電子書籍
- 逆鱗~黒龍の再臨~【タテヨミ】第13話…
-
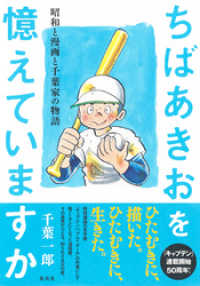
- 電子書籍
- ちばあきおを憶えていますか 昭和と漫画…
-
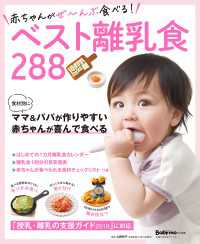
- 電子書籍
- 赤ちゃんがぜ~んぶ食べる!ベスト離乳食…