内容説明
近現代の日本文学史を担ったひとびと。明治二十三年から昭和二十四年の『校友会雑誌』『向陵時報』に一高文学の血脈を読む。
目次
1 明治期(一八九〇~一九一二)(一高『校友会雑誌』創刊のころ―大町桂月、上田敏、武島羽衣、尾上柴舟;個人主義の台頭―石原謙、藤村操、魚住影雄、阿部次郎、安倍能成;文学の興隆 詩歌、俳句―茅野肅々、木下杢太郎、荻原井泉水、吉植庄亮、土屋文明 ほか)
2 大正期(一九一二~二六)(「愛と認識への出発」倉田百三;哲学と文化史への志向―谷川徹三、三木清、林達夫、北川三郎;新感覚派、新興芸術派への胎動―芹沢光治良、川端康成、池谷信三郎、村山知義 ほか)
3 昭和期―戦争と抑圧に消えざりし文学の灯火(しのびよる激動の間に―高見順、島村秋人、中島敦;受難と間奏譜―北川省一、塙正、森敦、杉浦明平、立原道造;新墾の駒場の時代―福永武彦、小島信夫、中村真一郎、加藤周一 ほか)
著者等紹介
稲垣眞美[イナガキマサミ]
1926年京都生まれ。東大文学部美学科卒、同大学院修了。作家、評論家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
K.H.
0
情報は多いが、力点がなんとなくぼやけていて、読後に残るものが少なかった。副題に「上田敏・谷崎潤一郎・川端康成(……)らの系譜」とあるけれど、“系譜”なるものがあったとしても、あまり読み取れない。あるのは旧制一高の校友会雑誌という”共通点”だけ。雑誌連載が元だったため仕方ないだろうか。それでも、今日では忘れられた才能を紹介するときの著者の筆は乗っていて、ここは面白く読めた。最後に、誤字脱字が少々目立つ。安倍能成が「安倍龍成」になっているところもあって、おいおい、となった。編集、ちゃんと仕事してたのかな。2020/11/02
-
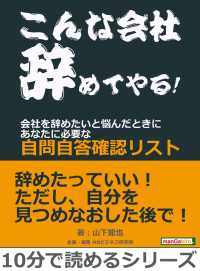
- 電子書籍
- 「こんな会社辞めてやる!」会社を辞めた…








