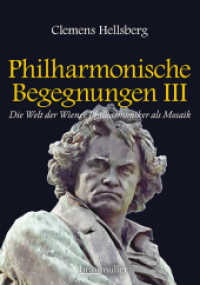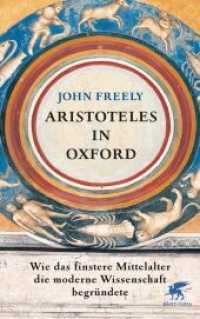内容説明
コミュニケーションについて問うことは、人間とは何か、について考えることである。コミュニケーションはいかにして可能かという問いに切り込む「沈黙の双子」、認知科学や人工知能におけるフレーム問題という難問に挑む「ロボットのジレンマ」、思弁的実在論の検討、さらには脳科学、精神分析における無意識、心理学や精神医学と社会学との接点に浮かび上がる諸問題を鮮やかに考察し、多彩な視点からコミュニケーションの本質に迫る。
目次
第1部 基礎理論(コミュニケーションの(不)可能性の条件―沈黙の双子をめぐって
フレーム問題再考―知性の条件とロボットのジレンマ
根源的構成主義から思弁的実在論へ―そしてまた戻る)
第2部 応用(交換に伴う権力・交換を支える権力;脳科学の社会的含意;精神分析の誕生と変容―二〇世紀認識革命の中で;女はいかにして主体化するのか―河合隼雄の『昔話と日本人の心』をもとに)
著者等紹介
大澤真幸[オオサワマサチ]
1958年、松本市生まれ。東京大学大学院社会学研究科博士課程修了。社会学博士。思想誌『THINGKING「O」』主宰。2007年『ナショナリズムの由来』で毎日出版文化賞を受賞。2015年『自由という牢獄』で河合隼雄学芸賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
33
著者は、第3次AIブームは、第2次AIブームのときと同じフレーム問題に躓いているといいます。それは、人間はどうやって主題領域を決めているのかという問題です。人間とチンパンジーの決定的な差であり、コミュニケーションとは何なのかということに直結しています。双子のエピソードは、人間を擬するAIをつくったときの本質に迫っています。双子は完全に同一ではなく、調和と葛藤が共に生じています。お互いは完全に同調することを嫌い、差異(他者性)を際立たせます。主体の欲望は直接対象には向かわず、嫉妬(他者の優位)という媒介を経2019/03/30
学び舎くるみ
10
宣教師と土人が川を船で渡る問題で、愚か者が上流に橋を作れば?なんていいだしたらどうなる?ってな話をフレーム問題の関連で例示する。言われて初めて、あ、その手があったかって思うのは無視するのとは違う。「愚か」を「思か」、「無視のようない消極的操作」なんてもはや解読不能。これほど誤字が多いと、ちゃんと読み返すこともしてないのだなと内容にも信頼が置けなくなる。だって、難しくてほぼ理解できないから、鵜呑みにする覚悟だったのに萎えるよね。というわけで、187ページで脱落2019/05/26
Go Extreme
1
コミュニケーション(不)可能性の条件:社会学の主題としてのコミュニケーション 沈黙の双子 関連性理論─フレーム問題の魔術的解決 嫉妬と抑制 他者の欲望 言語行為の構造 沈黙の構成 電話と郵便と魔法 アメリカと子どもと放火 内在と超越 フレーム問題再考─知性の条件とロボットのジレンマ 深層学習はフレーム問題を克服できるか 根源的構成主義から思弁的実在論へ 交換にともなう権力・交換を支える権力 脳科学の社会的含意 精神分析の誕生と変容─20世紀認識革命 女はいかにして主体化するのか─河合隼雄の昔話と日本人の心2019/09/18
-

- 電子書籍
- 人生最後の時間 - よく生ききった人た…