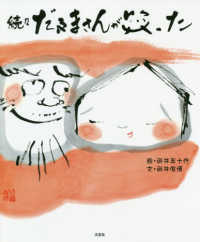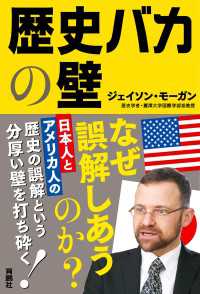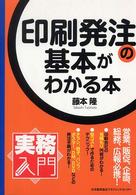内容説明
人と出会い、語りに耳を傾ける。そのフィールドワークという経験に、リアリティは感じられるか?認識論からインタビュー、作品化などの研究実践に至るまでを論じ、さまざまな論点を鋭く提起する。「個人の人生に向き合う社会学」の決定版。
目次
第1章 ライフストーリーとは何か
第2章 「口述の生活史」周辺
第3章 自己と語り
第4章 語りの時間
第5章 語りの共同構成
第6章 語りの構造
第7章 語りの様式
第8章 混沌の語り
第9章 歴史叙述のオーラリティ
第10章 インタビューの倫理
著者等紹介
桜井厚[サクライアツシ]
立教大学社会学部教授。1947年生まれ。東京都立大学大学院博士課程満期退学。南山短期大学講師、中京大学社会学部助教授・教授、千葉大学文学部教授を経て現職。日本社会学会、関西社会学会、日本オーラル・ヒストリー学会会員。専門は、ライフヒストリー/ライフストーリー/オーラルヒストリー研究、社会問題の社会学など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
子音はC 母音はA
3
インタビューを通して、その個人の歴史を拾う、そのものの行為に自覚的になって注意深く批判を加える思考が示されている。言語論的転回以後、この手法の繊細さが要求されてきたのがわかる。物語構造そのものも頭の片隅に入れときながら、それを回避し、一義的な変なレッテルを貼らないように絶え間ない粘り強い努力が必要である。2014/06/29
shimojik
0
体験:外的な行動として現れた振る舞い。経験:語り手のイメージ、感覚、感情、欲望、思想、意味などを伴って成立するもの/リンデ:自己の三つの特質、1.連続性がある。時間、その人の人生を越えて連続する。2.独自性がある。他者と区別される。アイデンティティの確立とは他者と関連して自己を語ること。3.再帰性がある。自己を語るとは反省すること。何者かを語ることで何者かが明確化する2013/01/03
yakisamako
0
ナラティブアプローチの意味がいまいちよくわからず本書に行きついた。ライフストーリーとは心理学用語も多々使用されるが、心理学的研究よりも社会学的研究の意味合いが強いこと。実証主義の強い歴史学において口述は軽視されてきたが、近年では口述資料の重要性が認識されてきた。インタビュアーと語り手相互行為によりライフストーリーは完成するなど、ほぼほぼ無知の自分でもある程度理解出来るような読みやすい内容であった。ただ本当に理解しているのかと言われたら困る。2021/07/26
たじー
0
卒論の参考にしようと思い読了。あとがきで著者も述べているように、教科書的にライフストーリーについて書かれたものではなく、ライフストーリーに関する情報が細切れに書かれているという印象。頭に残っていない部分が多いが、参考になった部分も確かにあった。2018/07/03
takao
0
ふむ2018/01/24