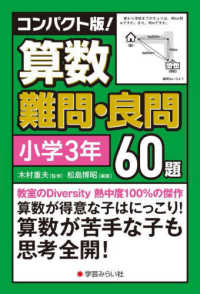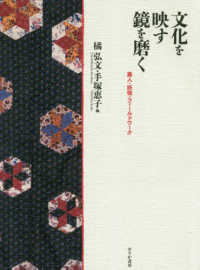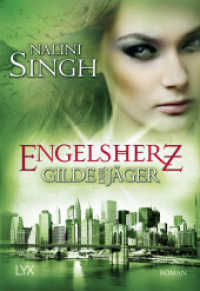- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
出版社内容情報
イギリス人ジャーナリストが、アマゾンUKの倉庫での作業員、Uberのタクシー運転など最低賃金の仕事に自ら就いて潜入取材。
内容説明
英国で“最底辺”の労働にジャーナリストが自ら就き、体験を赤裸々に報告。働いたのはアマゾンの倉庫、訪問介護、コールセンター、ウーバーのタクシー。私たちの何気ないワンクリックに翻弄される無力な労働者たちの現場から見えてきたのは、マルクスやオーウェルが予言した資本主義、管理社会の極地である。グローバル企業による「ギグ・エコノミー」という名の搾取、移民労働者への現地人の不満、持つ者と持たざる者との一層の格差拡大は、我が国でもすでに始まっている現実だ。
目次
第1章 アマゾン(ルーマニア人労働者;懲罰ポイント ほか)
第2章 訪問介護(介護業界の群を抜く離職率;観光客とホームレスの町 ほか)
第3章 コールセンター(ウェールズ;「楽しさ」というスローガン ほか)
第4章 ウーバー(ギグ・エコノミーという搾取;単純な採用試験 ほか)
著者等紹介
ブラッドワース,ジェームズ[ブラッドワース,ジェームズ] [Bloodworth,James]
英国人ジャーナリスト。現地で影響力のある左翼系ウェブサイト“Left Foot Forward”の元編集者。大手紙インディペンデントやガーディアン、ウォール・ストリート・ジャーナル等にコラムを寄稿
濱野大道[ハマノヒロミチ]
翻訳家。ロンドン大学・東洋アフリカ学院(SOAS)、同大学院修了(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
absinthe
えちぜんや よーた
R
TATA
Willie the Wildcat