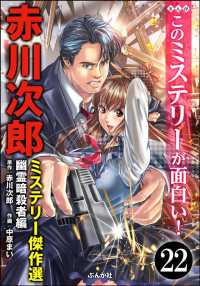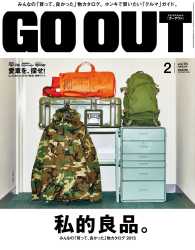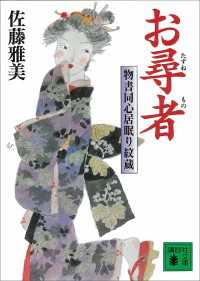- ホーム
- > 和書
- > 文庫
- > 雑学文庫
- > 光文社 知恵の森文庫
内容説明
「法隆寺は焼けてけっこう」「古典はその時代のモダンアート」「モーレツに素人たれ」―伝統とは創造であり、生きるための原動力であると主張する著者が、縄文土器・尾形光琳・庭園を題材に、日本の美の根源を探り出す。『今日の芸術』の伝統論を具体的に展開した名著、初版本の構成に則って文庫化。著者撮影写真、多数収録。
目次
1 伝統とは創造である(人力車夫と評論家たち;法隆寺は焼けてけっこう ほか)
2 縄文土器―民族の生命力(いやったらしい美しさ;狩猟期の生活様式が生む美学 ほか)
3 光琳―非情の伝統(真空に咲きほこる芸術;新興町人の精神と貴族性の対決 ほか)
4 中世の庭―矛盾の技術(なぜ庭園を取りあげるか;銀沙灘の謎 ほか)
5 伝統論の新しい展開―無限の過去と局限された現在
著者等紹介
岡本太郎[オカモトタロウ]
1911年東京生まれ。’29年渡欧。パリ大学に在籍し、哲学・社会学・民族学を学ぶ。抽象芸術運動に参加し、’40年に帰国。戦後、前衛芸術運動を再開。’51年に縄文土器と遭遇し、その衝撃を’52年に「四次元との対話―縄文土器論」(本書収録「縄文土器」)として発表。’54年に『今日の芸術』を著し、多大な反響を呼ぶ。’57年頃より「日本再発見」の旅を始める。’70年大阪万博に「太陽の塔」を制作。「芸術は爆発だ!」発現など、表現者としても多彩な才能を発揮。’96年の没後も作品展開催や著作復刊が相次ぐなど、「いま生きる人」を魅了し続けてやまない
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Y2K☮
こたけ正義感そっくりおじさん・寺
ホークス
さきん
ロビン