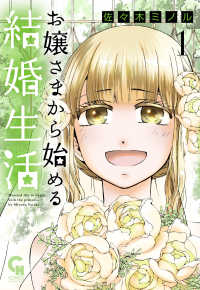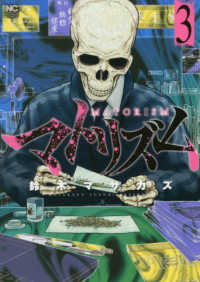内容説明
半地下の部屋で一日中パンを作らされている俺たちには、毎朝やってくる小間使いターニャの存在だけが希望の光だった。だが、伊達男の登場で…。底辺で生きる男たちの哀歓を歌った表題作、港町のアウトローの郷愁と矜持を生き生きと描いた「チェルカッシ」など、初期・中期の4篇。
著者等紹介
ゴーリキー,マクシム[ゴーリキー,マクシム] [Горький,Максим]
1868‐1936。ロシアの作家・ジャーナリスト。ニジニー・ノヴゴロド(1932‐90年まで彼にちなみゴーリキーと呼ばれた都市)の商人階層の家に育つ。困窮のため11歳から働き始め、20代まで各地を放浪した後、その経験を基にした短篇を次々と発表。1898年には作品集『記録と短篇』が刊行され好評を博す。革命運動にも関与しつつ、戯曲『どん底』、長篇『母』などを執筆し、「プロレタリア文学の父」とも呼ばれた。革命後は、ボリシェヴィキ政権と対立してイタリアに移るが、やがて擁護に転じ、1933年に帰国。その後はソ連の文化政策に協力する一方、体制に順応できない知識人の擁護にも尽力した
中村唯史[ナカムラタダシ]
1965年北海道生まれ。東京大学大学院人文科学研究科露語露文学専攻博士課程退学。モスクワ大学留学、山形大学教授などを経て、京都大学教授。専門はロシア文学・ソ連文化論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ケイ
143
「二十六人の男と一人の女」「グービン」「チェルカッシ」「女」の4つの短編。表題作「二十六...」は1番短いが、その中で男女の間における不変の真実を描いていると思った。チェーホフの「犬を連れた奥さん」と似た読後感。「チェルカッシ」人の心の弱さや地獄への穴へのはまりやすさと同時に、捨て置けないのが人の心の柔軟さ。これも時代や国を問わず普遍だろう。そして「女」で描かれる不幸せと憐憫のさまも見事。2019/03/13
ころこ
38
『26人の男と一人の女』以前、筒井康隆『短編小説講義』で絶賛していたのを導き手にして読んだときは、「26人の男が集合的人格として捉えられている」とあったと記憶しています。今回、新訳で読んでみて、26人の男の視線が部分的に塞がれていることの効果に気付きました。独特の雰囲気は「ガラスには穀粉がこびりついていたから、陽の光が部屋に射すことはなかった。」「中庭に面した板張りの戸板の割れ目にへばり付いた。」外界がみえない代わりに歌をうたい、普段は視線を送ることができないターニャへの想いは歪んだものになります。急速に2019/08/12
ビイーン
30
ゴーリキーは社会主義リアリズムの創始者と呼ばれるそうだ。短編作品はどれも底辺で生きる救いようがない人々の悲哀が描かれていた。「女」で主人公が言う言葉が強く印象に残る。「人々はぶざまに生きているよ―不和や卑小のなかで、貧困や愚劣なことに数えきれないほどに侮辱されながら」。今、自由主義の価値観が中国に代表される全体主義と対峙し覇権を争う中にいる。コロナの影響で働き方が変わる。そして私もこの流動化し既存の価値観が通用しなくなりつつある社会の中でぶざまに生きているのだ。2020/09/20
Porco
21
短編4作を収録。ゴーリキーは初めて読みました。社会主義リアリズムの作家だと聞いていましたが、収録されているのは政治色の薄い作品ばかり。プロレタリア文学と言われれば納得で、社会に底辺で放浪する人たちを描いています。解説も充実していて勉強になりました。2020/12/24
ぺったらぺたら子
18
『女』が最高。流浪者たちが野良犬の様になってひたすら地べたでごろごろしたり喧嘩したり。もう人間としてぎりぎりの底。語り手はその中に居ながらも決して混ざり合う事はなく、観察者として醒めながらも、熱く美を目指し、見詰める。「私は生のすべてを美しく誇り高いものとして目にしたい」。そして知り合った女の魂と共鳴共感しつつ、しかし混じり合う事はない。私は『猟人日記』の進化形とも感じた。もはや人間ではないぎりぎりの場所に、それでも立ち現れるもの、それこそ人間の証だろう。スタインベックのロシア版の様な風合いもあった。 2019/06/07