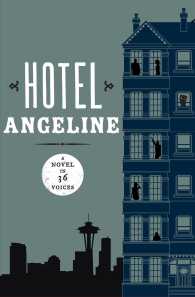出版社内容情報
ハイデガー[ハイデガー]
中山元[ナカヤマ ゲン]
内容説明
現存在とは「みずからおのれの存在へとかかわっている」存在者であること、つまり現存在は実存する。この第二分冊では、その実存の概念として「そのつどわたし」である各私性、平均的な日常性の概念が提起され、現存在の基本的な構造が「世界内存在」であることが詳細に考察される。
目次
第1部 時間性に基づいた現存在の解釈と、存在への問いの超越論的な地平としての時間の解明(現存在の予備的な基礎分析(現存在の予備的な分析の課題の提示;現存在の根本機構としての世界内存在一般;世界の世界性))
著者等紹介
ハイデガー,マルティン[ハイデガー,マルティン] [Heidegger,Martin]
1889‐1976。ドイツの哲学者。フライブルク大学で哲学を学び、フッサールの現象学に大きな影響を受ける。1923年マールブルク大学教授となり、’27年『存在と時間』を刊行。当時の哲学界に大きな衝撃を与えた。翌’28年フライブルク大学に戻り、フッサール後任の正教授となる。ナチス台頭期の’33年に学長に選任されるも1年で辞職。この時期の学長としての活動が、第二次大戦長後から多くの批判をうける。大戦後は一時的に教授活動を禁止された
中山元[ナカヤマゲン]
1949年生まれ。哲学者、翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
hitotoseno
6
本巻では現存在は本質ではなく実存であること、実存にはアリストテレスやカントが使うようなカテゴリーではなく独自の実存カテゴリーと呼ぶべきものがあてがわれるべきこと、従来の哲学は人間を被造物(眼前存在)として扱ってきたが、そうではなく事実的な生を克明にとらえるべきこと、そしてその事実的な生は「世界-内-存在」と呼ばれるのがふさわしいことなどが扱われる。他の箇所に比べれば(入門書や解説書でしばしば扱われているだけあって)わかりやすい部分だ。2021/04/06
tsukamg
4
読むのに一ヶ月かかった。1巻と同じく、本編を読んでもまったくわからず、解説を読んでわかったような気になった。オレらが生きていると、周りは道具が沢山ある。無意識に使っているから、いちいち「道具よのう」などと思っちゃいないが、ひとたび壊れて本来の機能を持たなくなったとたん、「おぬしはなんと道具であったことか」と、存在を意識できるようになる、とかいう解説が面白かった。2021/10/31
tieckP(ティークP)
4
相変わらず訳文は読みやすい。解説は誤字というか文として乱れるところがあって、やや校正不足な気がする。本文が明解なところの解説が多すぎる気もするが、やはり助かることも多い。ドイツ語のumの時間を表す意味の説明は間違っているので辞書を参照いただきたい(umは特定の時間の前後や頃ではなく、ぴったりその時間を指す前置詞。時期を指すときだけアバウトになる)。本文の内容はいまのところピンと来ない。カントの目的論と一般の小説からだけで、僕はここまでの内容は把握していて、それが難しく表現されているだけのような気がする。2018/05/03
いとう・しんご
2
やっぱり訳者解説が全体の半分強。ありがたくもあり、迷惑でもあり・・・岩波文庫版で最初から読み直そうかなぁ・・・2021/08/06
わたる
1
第2巻では、現存在のあり方と世界のあり方について見ていく。現存在からスタートして大枠から見ていくのだ。 まず全存在のあり方の点で重要な用語は、「本来性/非本来性」と「平均的なあり方」だろう。現存在は自らの持つ可能性から選んだあり方で存在している。自ら選択するのが本来的なあり方なのだ。しかし日常では可能性を無視して”非本来的”にある。とはいえ非本来的なあり方が必ずしも悪位わけではなく、通常のあり方を「平均的なあり方」として、分析の対象とする。この本来性などは、その後出てくる「頽落」に深く繋がっていると思う。2022/10/25